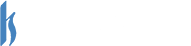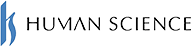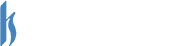取材ご協力:東京海上日動火災保険株式会社
マーケット戦略部 地域連携室
(お写真左から)
プロジェクト対応チーム:青池様、岡様 保険業務対応チーム:角様、西川様
東京海上日動火災保険株式会社 会社概要
・創業:1879年8月
・資本金:1,019億円
・従業員数:16,296名(2024年3月31日時点)
・事業内容:損害保険業、業務の代理・事務の代行、確定拠出年金の運営管理業務、自動車損害賠償保障事業委託業務
ご利用サービス・取り組み
- ・業務と既存ドキュメントの棚卸し、可視化ご支援
- ・業務マニュアル作成・改善・更新
マーケット戦略部の部門全体に、マニュアルを通じた業務改善が波及した事例です。
はじまりは、プロジェクト対応チームの取り組みでした。当チームでは、これまで経験のない新たなプロジェクトを進めるにあたり、ヒューマンサイエンスの支援のもと、関係者の共通認識をつくるためのマニュアル整備に取り組みました。まずは、大量の既存資料とヒアリングをもとに、業務の棚卸しと可視化をすることから着手しました。その後、業務フローを最適化したうえで、マニュアルを作成しました。
この最初の取り組みをきっかけに、アウトソースによる業務の棚卸しとマニュアル整備のメリットが部内外で注目されることとなり、他チームや他部門へも横展開が進んでいます。
今回は、マーケット戦略部のプロジェクト対応チームの青池様・岡様と、その後に別業務でのマニュアル整備を担当された、保険業務対応チームの角様・西川様にお話を伺いました。
ヒューマンサイエンスを選んだ理由
――マニュアルのアウトソーシングを検討されたきっかけを教えてください。
青池様:数年前、ある新規プロジェクトを立ち上げた際に、営業や代理店の方々に配布する手順書が必要となり、手探りで資料を準備しました。しかし、膨大な資料をうまくまとめることができず、「全体像がわかりにくい」「必要な情報がどこにあるかわからない」といった声が多く寄せられました。より使いやすいものに改善する必要がありましたが、プロジェクトメンバーのリソースがひっ迫していたため、社内での改善は難しい状況でした。そこで、マニュアル作成をアウトソースできないかと考えました。
――ヒューマンサイエンスを選んでいただいた理由をお聞かせください。
青池様:マニュアル作成をアウトソースした経験がなかったため、まずネットで検索してみました。そこでヒットしたのがヒューマンサイエンスでした。ホームページを確認したところ、信頼性が感じられたので、問い合わせをしてみました。アウトソーシングには、情報漏えいなどのセキュリティ面での懸念もありましたが、当社と同じ保険業界や金融業界での実績があることを知り、安心感を持てました。 また、初回の打ち合わせでは、こちらの課題と要望をしっかりと汲み取っていただき、マニュアル化の前段階である、業務の棚卸しまで並走してサポートいただける提案であったことも決め手の一つです。
部門内でのマニュアル改善波及
――最初にプロジェクト対応チームでマニュアルを整備されました。その後、どのようにして保険業務対応チームへとマニュアル整備の輪が広がっていったのでしょうか
青池様:部門内のチーム間連携を図るための報告会で、マニュアル整備をアウトソースしたことを共有しました。他チームのメンバーが、改善されたマニュアルの分かりやすさを見て「自分たちのチームで抱えている課題も、アウトソーシングによって解決できるのではないか」という話があがり、横展開していったという経緯です。
――保険業務対応チームは、プロジェクト対応チームでのマニュアル整備の事例を知って、どのように感じましたか
角様:報告会で見たマニュアルが、第三者の目線で体系立ててわかりやすく改善されていたので、アウトソーシングに魅力を感じました。 私たちのチームにはかなり多くのマニュアルがありましたが、散在していて体系的に整理されていないため、それぞれの関連性が分かりにくく、メンバーが十分に活用できる状況ではありませんでした。そのため、マニュアルを整理して、必要な情報を探しやすくするための枠組みを整備したいと考えていました。 青池さんに、ヒューマンサイエンスの業務の棚卸しの進め方を聞いて、私たちの課題もアウトソーシングで解決できるのではと考え、相談させていただきました。
西川様:実際に業務を担当している人がマニュアルを作ると、どうしても分かりづらくなったり、時間の制約もあったりします。社内でのマニュアル整備に課題を感じていた中で、プロジェクト対応チームの事例を知り、アウトソーシングでここまでの品質のマニュアルを整備できるのは、良い選択肢だと考えました。
プロジェクトの進め方
――みなさま、マニュアル整備を進めてみてどのようなことを感じられましたか
青池様:当社では、これまで業務の引き継ぎは口頭伝承であることが多く、自分を含め文字に起こすのが苦手な人が多い印象です。ヒューマンサイエンスに依頼する以前に、新たなプロジェクトについて、チームメンバーでかなり多くのディスカッションをしました。しかし、それをどのように文章化すれば関係者に適切に伝えられるかが、当初は悩ましいところでした。そこをヒューマンサイエンスが業務の棚卸しからサポートしてくれて、文章化したかった部分を、漏れなくマニュアルに落とし込んでもらえたので助かりました。
岡様:自分たちでいきなりマニュアルを作ろうとしても、手が止まったり、後戻りがあったり、うまく進められなかっただろうなと思います。依頼した当初は分かりませんでしたが、実際に進めてみて、業務とドキュメントを体系的に整理したうえで客観的にわかりやすいアウトプットをしてもらえることが、ヒューマンサイエンスに依頼する一番の魅力だと感じました。
角様:事前に渡した資料を読み込み、どういうマニュアルを目指すのかを協議して、方向性を取りまとめたうえで、ヒアリングを行ってくれました。ヒアリングでの質問を通じて、第三者視点での分かりにくい部分に気づくこともできました。自分たちで見落としがちなポイントをしっかりカバーしてもらえて、大変助かりました。
西川様:私たちの業務は、マニュアルがまったくないわけではなかったのですが、情報が点在していました。それを1つにまとめ、統一された形で整理してもらえたのはありがたかったです。
マニュアル整備による効果
――マニュアル整備を終えて、プロジェクト対応チームでは、どのような効果を感じましたか
青池様:プロジェクトに関する社内アンケートで、「全体像が見えやすくなった」「マニュアルがありがたかった」といった声が多く寄せられました。最近では、業務担当者から変更点の反映漏れを指摘されることもあり、現場でマニュアルが活用されるようになった証拠だなと、マニュアル整備の効果を感じています。 また、当初は想定していませんでしたが、業務の引き継ぎにもマニュアルが活用され、異動者や新メンバーの負担軽減になっていることも成果の1つです。
岡様:1,300~1,400名くらいを対象に、定期的に内部向け研修を実施しています。マニュアルに基づいた説明を行うことで理解度が向上したため、問い合わせ件数の減少や、問い合わせの質が改善していると感じています。私は途中からプロジェクトに参加したのですが、マニュアルを見て業務内容を理解したうえで携わることができ、スムーズにプロジェクトに入れたことが、とてもありがたかったです。
――保険業務対応チームでは、どのような効果を感じましたか
角様:新メンバーが配属されたときに、新しいマニュアルを早速活用しました。点在していたマニュアルを1つにまとめて業務フローを可視化してもらったので、教える側も伝達漏れがなく、教わる側も自分の立ち位置がわかり、安心感につながったのではないかと思います。新メンバーの中には、わからないことを人に聞くことにハードルを感じる方もいるかもしれません。1人で立ち返れるものがあることは、ストレス軽減にもつながっているのではないかと思います。
今後の計画・展望
――最後に、今後のビジョンや展望をお聞かせください
岡様:当社は転勤や異動が多い環境にあります。担当業務や環境が変わっても同じ熱量で業務を引き継いでいくために、業務を文字に起こしていくことは最も重要な取り組みだと言っても過言ではありません。ひいては、それがサステナブルな取り組みにつながっていくものだと思います。業務マニュアルを作成することは、思いを繋いでいく体制作りにもなり、その大切さを学びました。今後もマニュアル整備を継続していきたいです。
角様:マニュアルを活用して、業務の教育動画コンテンツを作成したいと考えています。新メンバーや異動者が、スムーズに業務開始できる環境を整えることで、組織全体の生産性向上を図っていきたいです。
西川様:マニュアルを「作って終わり」にするのではなく、定期的な見直しや改善を行い、最新情報を常に提供できる状態を維持していきたいです。マニュアルを作成する際は、フラットな情報提供も大切ですが、熱量が伝わる工夫も続けていきたいと思います。
関連サービス・ブログ
他社のマニュアル作成事例を徹底紹介!他社事例から学ぶ
マニュアル作成の進め方
マニュアル作成に着手する前に、他社のマニュアル作成事例を知ることで、「作成のポイント」や「つまづきがちな課題」を把握し、マニュアル作成のヒントとすることができます。
こんな方におすすめです
- ・マニュアル作成を進めたいがボリュームが多すぎて何から手をつけていいか分からない
- ・自社でやりたいことができるのか分からない
- ・他社でどのようにマニュアル作成を進めているのか知りたい

【ご紹介企業様】
- 株式会社東通メディア様
- 株式会社BANDAI SPIRITS様
- 株式会社NTTデータ関西様
- 株式会社SBI証券様
- NTTデータ カスタマサービス株式会社様
- ウイングアーク1st株式会社様
- 日本板硝子株式会社様