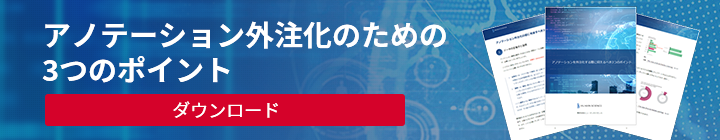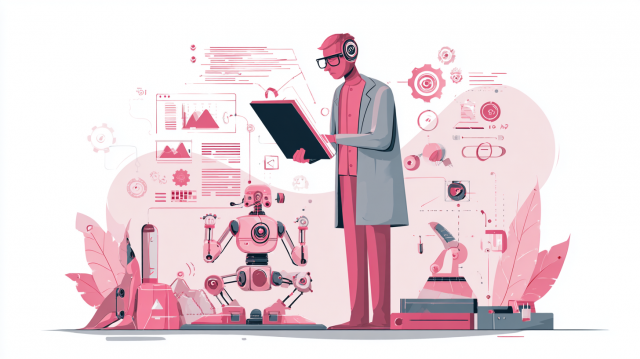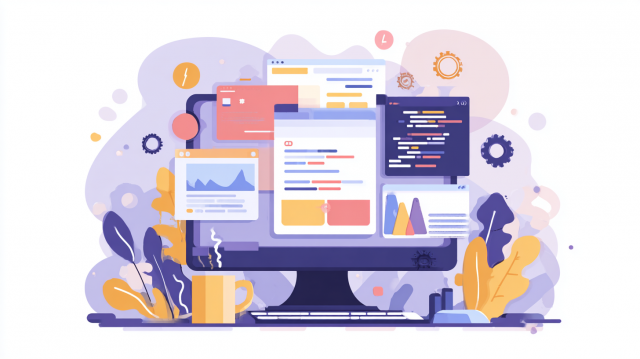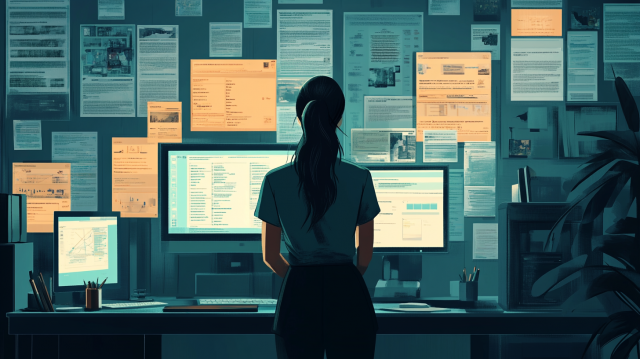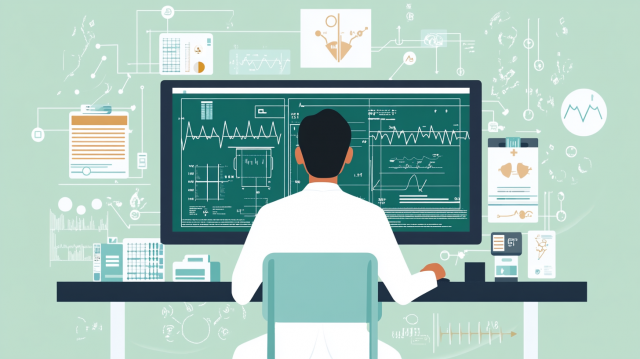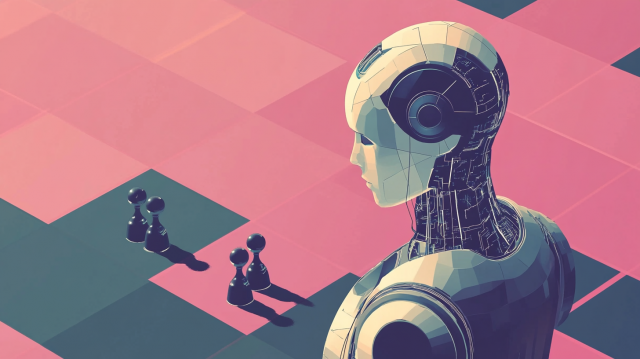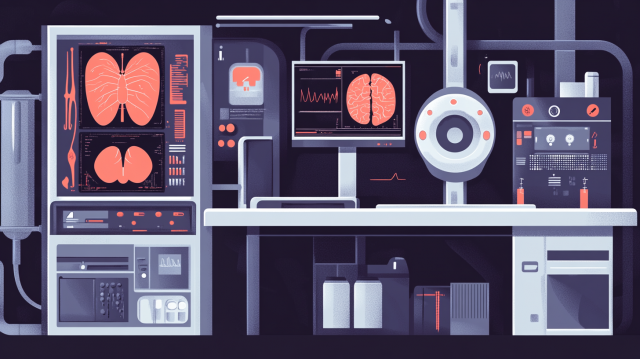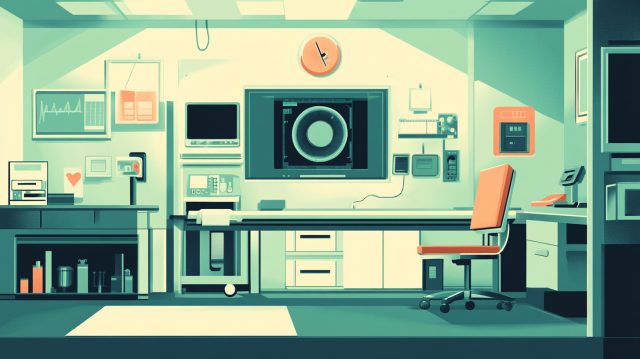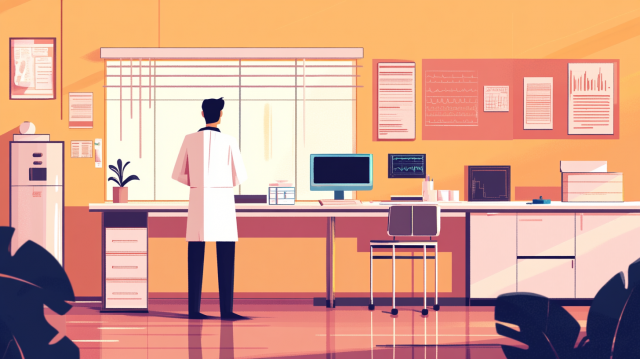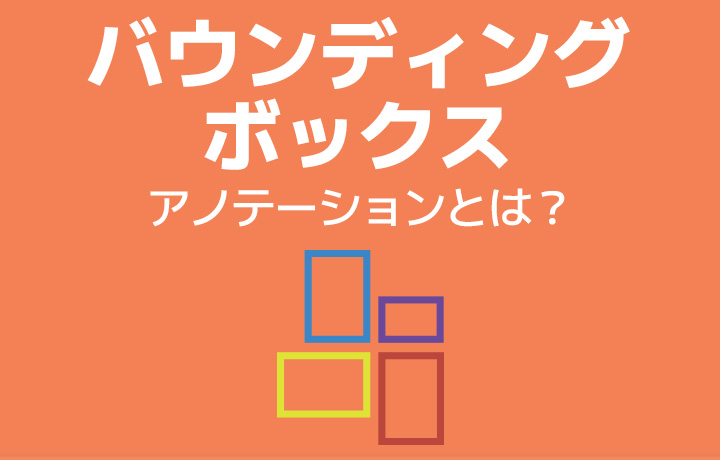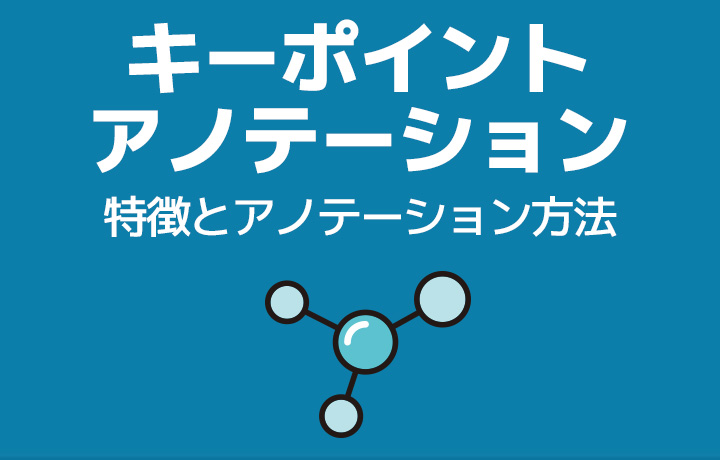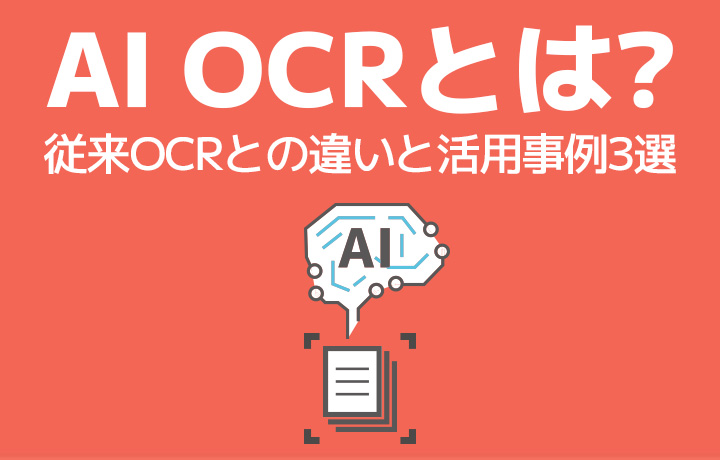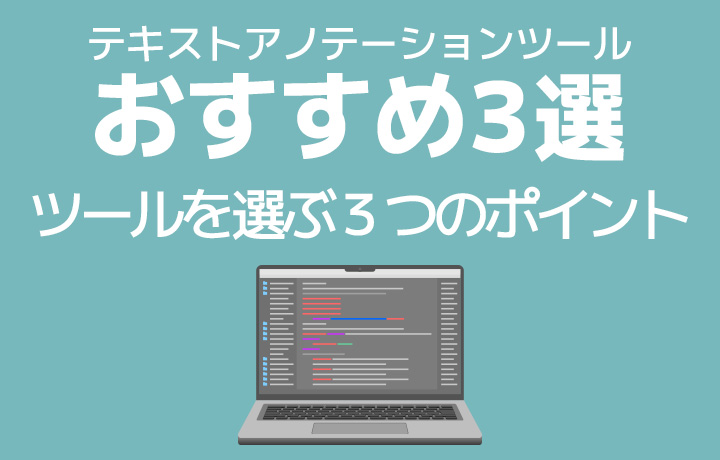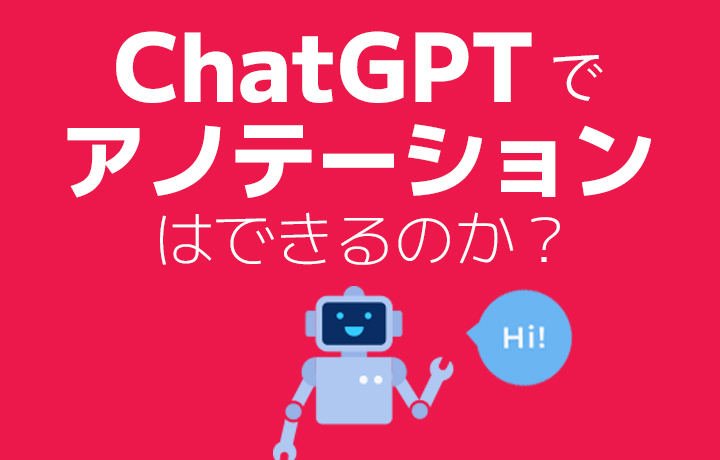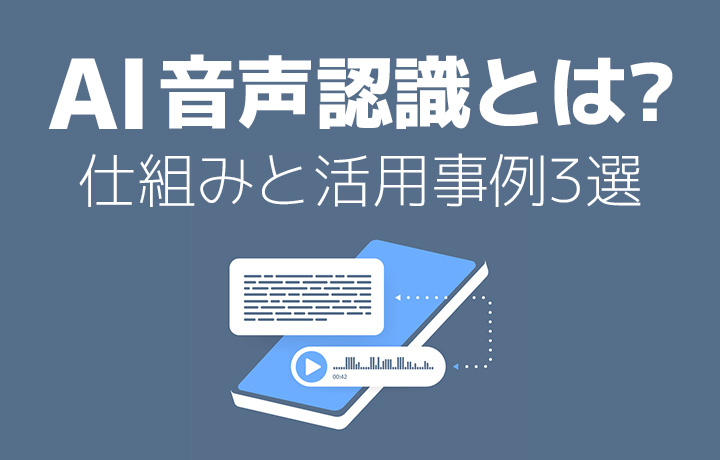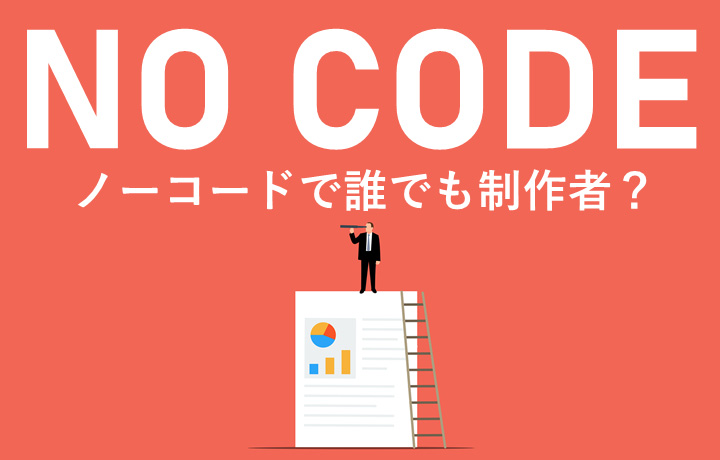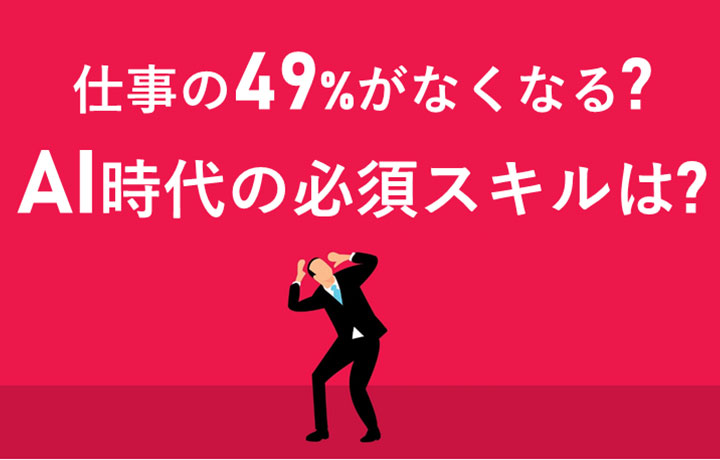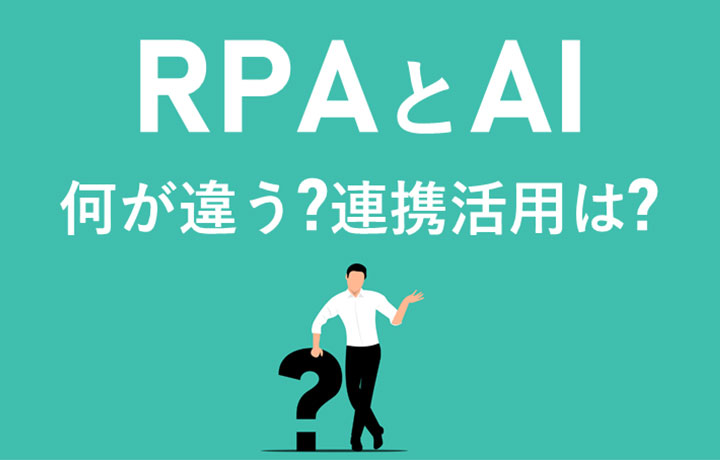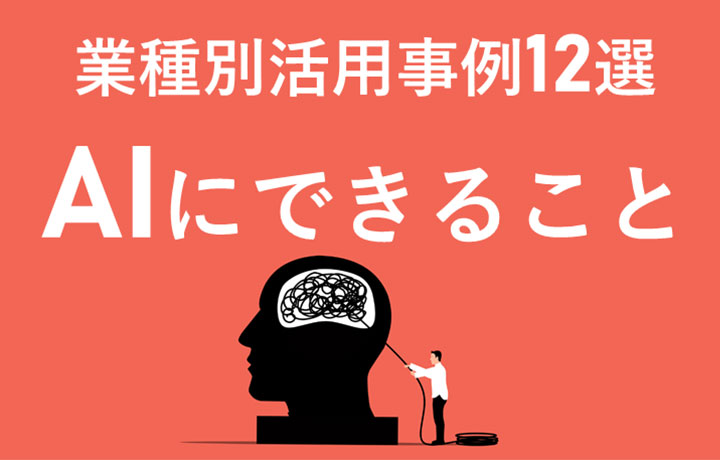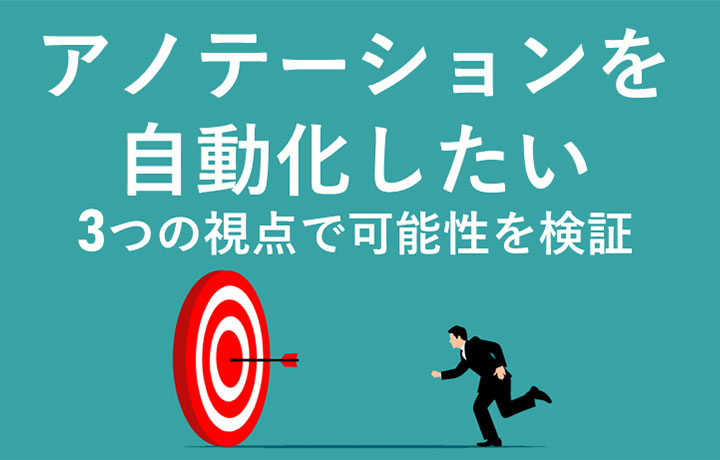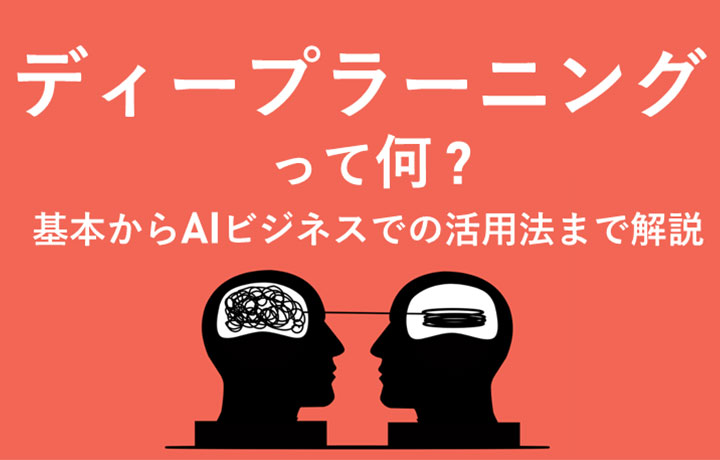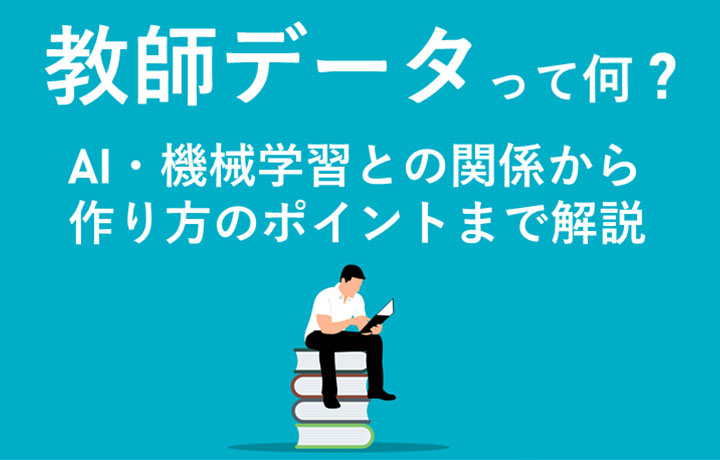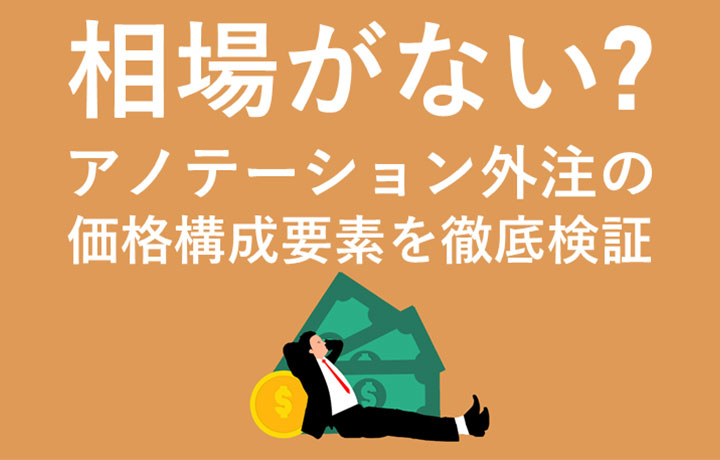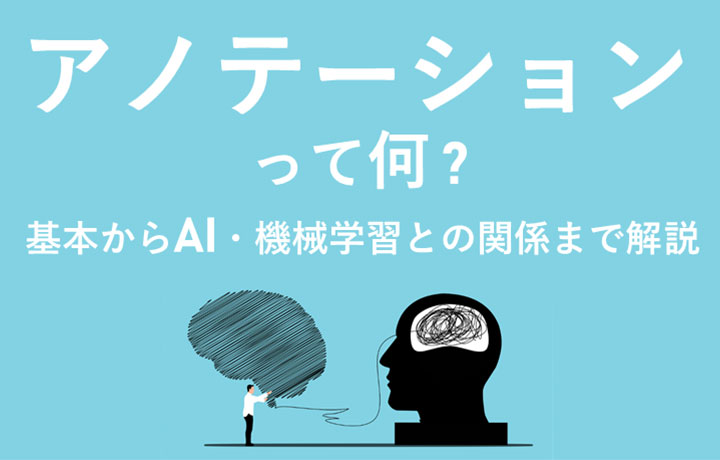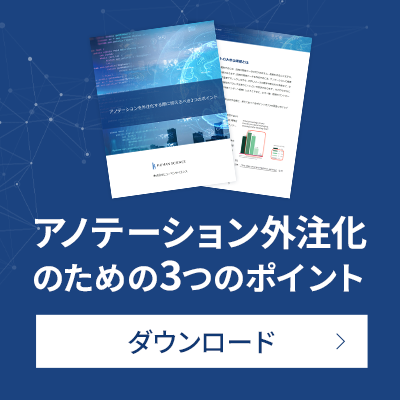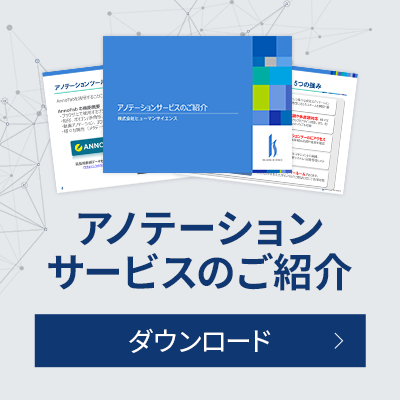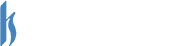- 目次
-
- 1. 製造業DXの現状と生成AIへの期待
- 2. 生成AIが変える主要領域と製造業DXへの効果
- 2-1. 設計・開発における生成AI活用
- 2-2. 生産現場のDXと生成AI
- 2-3. 品質管理の高度化
- 2-4. サプライチェーンと経営管理における生成AIの活用
- 3. 国内外における製造業DXと生成AIのユースケース
- 3-1. Bosch:生成AIを用いた不良品画像の生成による品質モデル強化
- 3-2. GA Telesis:見積プロセスの自動化支援
- 3-3. 本田技研工業(Honda):熟練技術者ノウハウの抽出・構造化
- 3-4. AGC:技術ナレッジへのRAG型AI応答基盤
- 4. 製造業DXにおける生成AI導入の課題とリスク
- 5. 製造業DXに不可欠な生成AIデータ基盤整備
- 6. まとめ
- 7. ヒューマンサイエンスの教師データ作成、LLM RAGデータ構造化代行サービス
1. 製造業DXの現状と生成AIへの期待
製造業におけるDXは、これまで生産効率を高めることを主な目的に進められてきました。IoTで設備の稼働状況を把握したり、RPAで事務処理を自動化したりといった取り組みは多くの現場で導入されています。
しかし現実には、人材不足や技能継承の停滞、国際競争の激化、地政学的リスクによるサプライチェーンの混乱、さらにカーボンニュートラル対応やESG要請など、企業が直面する課題は拡大し続けています。従来の「効率化中心」のDXでは、こうした環境変化に追いつけなくなりつつあります。
こうした中で注目されるのが「生成AI」です。生成AIは、ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)や画像生成モデルを用い、過去の知識やデータをもとに新しい文章・設計・アイデアを生み出す技術です。これにより、従来の自動化では難しかった「知識活用」「付加価値創出」が可能になってきました。生成AIは製造業DXを次の段階へ進めるための大きなカギになると期待されています。
参考ブログ:
RPAを基本から解説。AIとの違いは?RPAとAIを連携させた活用法も紹介。
AI×IoTの活用事例4選。IoT市場の2023年はどうなる?
業務効率化に活かすLLMとRAGとは?生成AIのビジネス活用法を解説
2. 生成AIが変える主要領域と製造業DXへの効果
生成AIは、製造業の幅広い領域に変化をもたらす可能性を秘めています。単なる省力化やコスト削減にとどまらず、現場に蓄積されながら活用されていない知識やデータを整理し、誰でもすぐに使える形にすることができます。これにより、これまで時間をかけて探さねばならなかった情報などに即座にアクセスできるようになり、さらに膨大な文書からポイントをまとめることも瞬時に行えるため業務スピードが上がり、さらには迅速な意思決定が可能になるでしょう。さらに、過去の知見を組み合わせて新しい設計案や改善策を導き出すことで、従来の方法では思いつかなかったような新たな価値創出も期待できます。
では具体的に、製造業DXにおいて生成AIがどのような領域で活用され、どんな変化をもたらすのかを見ていきましょう。
2-1. 設計・開発における生成AI活用
過去の設計データやCAE解析情報をもとに、新しい設計案を自動生成することが可能になるでしょう。これにより従来なら数日かかっていた試作検討が数時間で可能になり、製品開発のスピードが飛躍的に向上します。
また、CADモデルから仕様書を自動作成し、設計レビューを効率化することで、設計ミスの早期発見や部門間の連携強化にもつながります。
2-2. 生産現場のDXと生成AI
作業マニュアルや教育教材を生成AIで自動作成することで、短期間で現場に共有できます。新任者でも短期間で一人前になれる環境を整えることができ、人材不足への対応策となります。
さらにIoTやMESデータを生成AIがわかりやすいレポートにまとめることで、現場リーダーが迅速に状況を判断できるようになり、トラブル対応や改善活動のスピードが格段に上がります。
2-3. 品質管理の高度化
不良発生ログや検査結果を生成AIが解析し、改善策を提案するレポートを自動生成します。これにより、品質改善サイクルが加速し、従来より短期間で歩留まりを改善できます。
また、社内品質マニュアルを自然言語検索可能にすることで、担当者は「必要な情報にすぐにアクセス」でき、問い合わせ対応や教育工数を大幅に削減できます。
2-4. サプライチェーンと経営管理における生成AIの活用
市場や調達データを解析し、需要予測やリスクシナリオを自動生成することで、突発的な供給不足や価格変動にも素早く対応できます。経営層の意思決定がスピードアップし、リスク回避力の強化につながります。
さらに、多言語での文書作成を自動化することで、海外拠点や取引先とのやり取りが格段にスムーズになり、グローバル展開のスピードを後押しします。
3. 国内外における製造業DXと生成AIのユースケース
こうした生成AIの可能性は、すでに国内外の製造業で検証され始めています。海外ではデジタルツインやシミュレーションと組み合わせた活用が進み、日本国内でも教育や品質管理の分野で実証実験が行われています。
ここでは、特に注目できる具体事例を四つ紹介し、どのような課題意識から導入に至ったか、どんな変化が生まれたかを見ていきます。
3-1. Bosch:生成AIを用いた不良品画像の生成による品質モデル強化
ドイツのロバート・ボッシュ(Bosch)は、製造ラインでの自動光学検査を強化するために生成AIを活用しています。
●背景・課題:実際に発生する欠陥パターンのすべてを画像として収集するのは現実的ではなく、データが不足しやすい。
●取り組み内容:生成AIで人工的に欠陥画像を生成し、良品/不良品判定モデルのトレーニングに活用。実際の画像データと生成画像を組み合わせて学習させる戦略が取られています。
●成果:AIモデルのトレーニング期間短縮などが報じられており、生成AIを使うことで、従来よりも早く品質検査システムを強化できる可能性を示した事例です。
3-2. GA Telesis:見積プロセスの自動化支援
米国の航空機部品・整備企業 GA Telesis は、非定型・複雑な見積依頼に対して生成AIを導入し、営業応答プロセスを効率化しています。
●背景・課題:見積依頼は多様でかつ短納期が求められることが多いが、従来の手動対応では時間がかかる。
●取り組み内容:Google Cloud の生成AIを使って、見積依頼文書を解析し、発注書や回答案を自動生成するシステムを導入。営業担当者の作業負荷を削減することを目的としています。
●成果:従来の手作業での在庫照会や参照作業を削減し、より迅速な顧客対応を実現。営業プロセスの応答速度と柔軟な対応力を高めています。
3-3. 本田技研工業(Honda):熟練技術者ノウハウの抽出・構造化
日本のホンダ(Honda)は、社内に散在する設計資料や技術ノウハウをデータベース化・再利用可能にするため、生成AI/LLMを活用した取り組みを進めています。
●背景・課題:熟練技術者の暗黙知が PowerPoint や設計図などに分散し、そのままでは検索性・再利用性が低い。
●取り組み内容:資料や図表からテキストを抽出し、構造化する技術を導入。生成AIを使って、これらのデータを知識ベース化し、RAG 等で生成AIが参照しやすい形に整備。
●成果:知識伝承・情報検索性の向上、モデリング期間の短縮などが報告されており、熟練者のノウハウが若手や他部署でも活用しやすくなり、知識継承と組織全体での技術力強化につながっています。
3-4. AGC:技術ナレッジへのRAG型AI応答基盤
化学・ガラス材料を手がける AGC は、社内技術ノウハウやトラブル対応知見をナレッジベース化し、RAG機能付きの生成AI応答システムを導入しました。
●背景・課題:技術者が必要な情報にたどり着くまで時間がかかることが業務効率の妨げに。
●取り組み内容:散在する資料を構造化し、生成AIを通じて自然言語で問い合わせできる仕組みを構築。
●成果:技術系問い合わせの応答が迅速化し、効率的な情報の利活用につながっています。
4. 製造業DXにおける生成AI導入の課題とリスク
生成AIには多くのメリットがある一方、導入にあたっては見逃せない課題やリスクも存在します。これらを軽視すると、期待した成果が得られないばかりか、逆に業務に悪影響を及ぼす可能性さえあります。
この章では、製造業が生成AIを導入する際に直面しやすい課題とリスクを整理し、注意すべきポイントを確認します。
まず、データガバナンスの問題です。設計書や生産データには知財や機密情報が含まれます。これらをAIに利用させる際には、適切なセキュリティとアクセス管理が欠かせません。
次に、生成AIの回答精度の問題です。生成AIは時に「もっともらしい誤情報(ハルシネーション)」を出力することがあります。これを防ぐには、人の検証や、RAGで信頼性の高いデータを参照させる工夫が必要です。
また、現場で受け入れられるかという課題もあります。AIの判断はブラックボックス的で、現場担当者が納得できない場合もあります。AIを適切に活用する全社的な取り組みが成功への鍵となるでしょう。
さらに、投資対効果(ROI)の可視化も重要です。生成AIを導入してどの程度の工数削減や品質向上が得られたのかを定量的に把握しなければ、果たして成功しているのかがわかりません。
5. 製造業DXに不可欠な生成AIデータ基盤整備
生成AIの成果を最大化するには、AIが参照するデータの質を高めることが不可欠です。製造業には膨大な設計書、マニュアル、検査レポート、作業ログがありますが、形式や表記がバラバラで、そのままではAIにとって扱いにくい「非構造データ」が大半です。
そこで重要になるのが、データ基盤の整備です。文書や設計データにタグを付けて分類し、専門用語を統一してAIが理解しやすい形にする。ドキュメントによっては、その内容に間違った情報や古い情報が混在している場合もありますし、ドキュメントそのものも鍼灸が混在している場合もあります。これらに対しては内容を精査して修正するなどデータクレンジングが必要です。さらにナレッジを小さな単位に分割して検索精度を高め、検査ログやレポートを正規化して一貫性を持たせる。こうした整備を行うことで、生成AIが「正しく検索し、正しく生成する」ことが可能になります。
これは従来のアノテーション(教師データ作成)ともつながる考え方です。識別系AIのためのラベリングに加えて、生成AI活用に適した知識の整理・構造化が、今後の製造業DXを成功に導く大きな要素となります。
6. まとめ
これまでの製造業DXは、IoTやRPAを活用した効率化が主な目的でした。しかし今後は、生成AIを取り入れることで、知識の活用や新たな価値創出へと進化していく必要があります。言い換えれば「効率化中心の段階」から「価値創出の段階」へとシフトしていくのです。
その実現には、まず高品質なデータ基盤を整え、生成AIが信頼できる情報を扱えるようにすることが欠かせません。そして、現場の担当者が日常業務の中で自然に使える仕組みを整備することも重要です。さらに経営の視点からは、投資対効果をきちんと測定し、自社の競争力向上にどの程度寄与したのかを明確にしていくことが求められます。
生成AIは単なる効率化のためのツールではなく、企業が業界内で競争力を再構築し、DXの新たなステージを切り開く存在になると考えられます。
7. ヒューマンサイエンスの教師データ作成、LLM RAGデータ構造化代行サービス
教師データ作成数4,800万件の豊富な実績
ヒューマンサイエンスでは自然言語処理に始まり、医療支援、自動車、IT、製造や建築など多岐にわたる業界のAIモデル開発プロジェクトに参画しています。これまでGAFAMをはじめとする多くの企業様との直接のお取引により、総数4,800万件以上の高品質な教師データをご提供してきました。数名規模のプロジェクトからアノテーター150名体制の長期大型案件まで、業種を問わず様々な教師データ作成やデータラベリング、データの構造化に対応しています。
クラウドソーシングを利用しないリソース管理
ヒューマンサイエンスではクラウドソーシングは利用せず、当社が直接契約した作業担当者でプロジェクトを進行します。各メンバーの実務経験や、これまでの参加プロジェクトでの評価をしっかりと把握した上で、最大限のパフォーマンスを発揮できるチームを編成しています。
生成系AI LLMデータセット作成・構造化、「AIに最適化するマニュアル作成・整備支援」にも対応
データ整理のためのラベリングや識別系AIの教師データ作成のみでなく、生成系AI・LLM RAG構築のためのドキュメントデータの構造化にも対応します。創業当初から主な事業・サービスとしてマニュアル制作を行い、現在では「将来的な生成AI・RAG導入・活用に向けての業務ナレッジ整備やマニュアル化の支援」も行っております。さまざまなドキュメントの構造を熟知している当社ならではのノウハウを活かした最適なソリューションを提供いたします。
自社内にセキュリティルームを完備
ヒューマンサイエンスでは、新宿オフィス内にISMSの基準をクリアしたセキュリティルームを完備しています。そのため、守秘性の高いデータを扱うプロジェクトであってもセキュリティを担保することが可能です。当社ではどのプロジェクトでも機密性の確保は非常に重要と捉えています。リモートのプロジェクトであっても、ハード面の対策のみならず、作業担当者にはセキュリティ教育を継続して実施するなど、当社の情報セキュリティ管理体制はお客様より高いご評価をいただいております。
内製支援
弊社ではお客様の作業や状況にマッチしたアノテーション経験人材やプロジェクトマネージャーの人材派遣にも対応しています。お客様常駐下でチームを編成することも可能です。またお客様の作業者やプロジェクトマネージャーの人材育成支援や、お客様の状況に応じたツールの選定、自動化や作業方法など、品質・生産性を向上させる最適なプロセスの構築など、アノテーションやデータラベリングに関するお客様のお困りごとを支援いたします。

 テキストアノテーション
テキストアノテーション 音声アノテーション
音声アノテーション 画像・動画アノテーション
画像・動画アノテーション 生成AI、LLM、RAGデータ構造化
生成AI、LLM、RAGデータ構造化
 AIモデル開発
AIモデル開発 内製化支援
内製化支援 医療業界向け
医療業界向け 自動車業界向け
自動車業界向け IT業界向け
IT業界向け 製造業向け
製造業向け