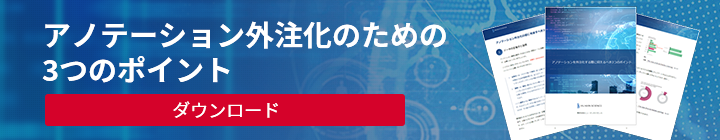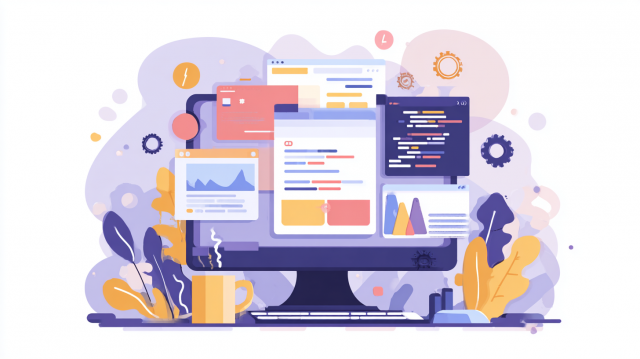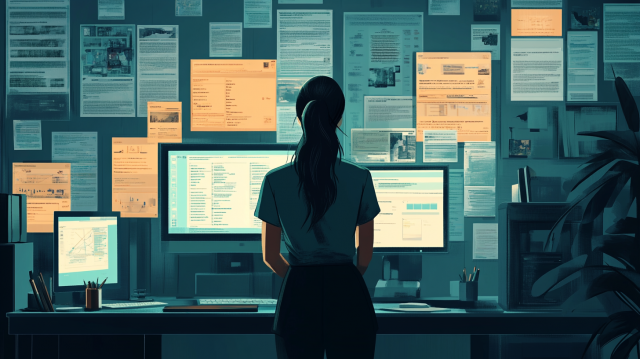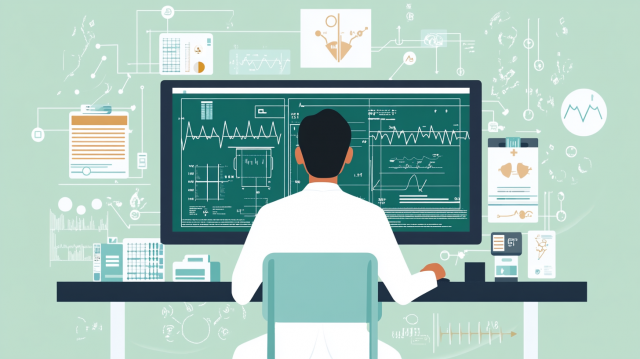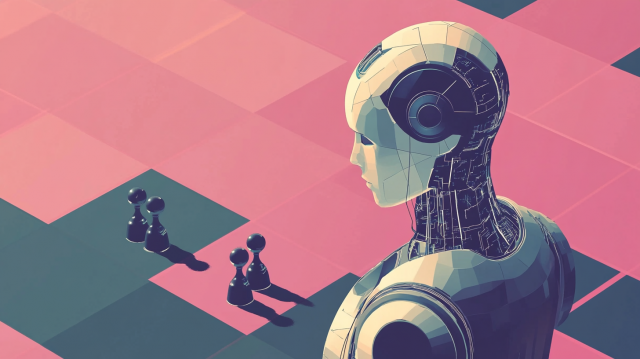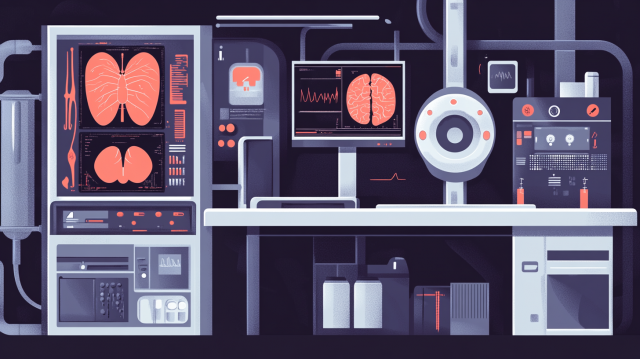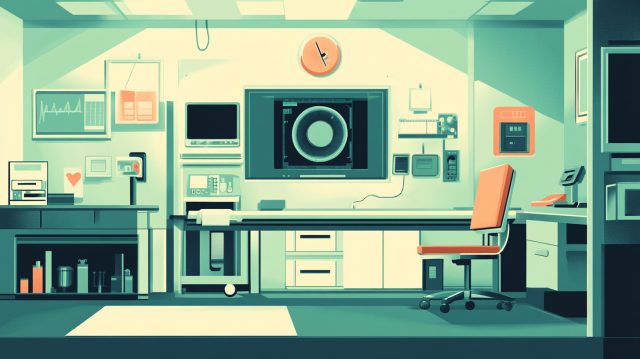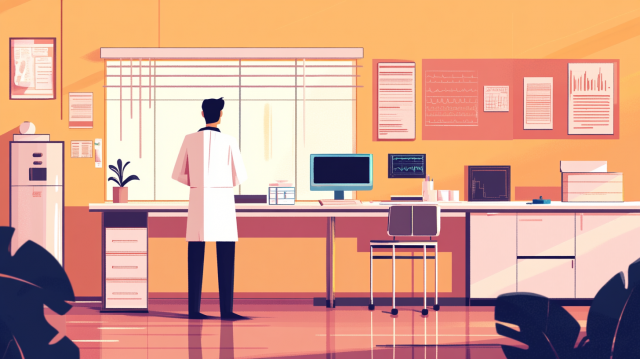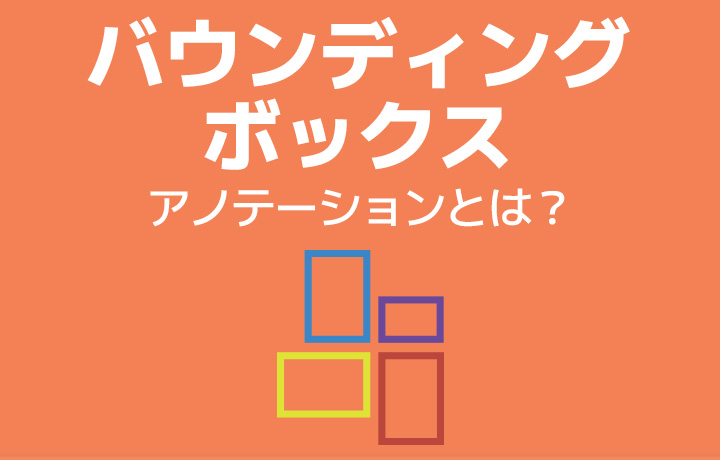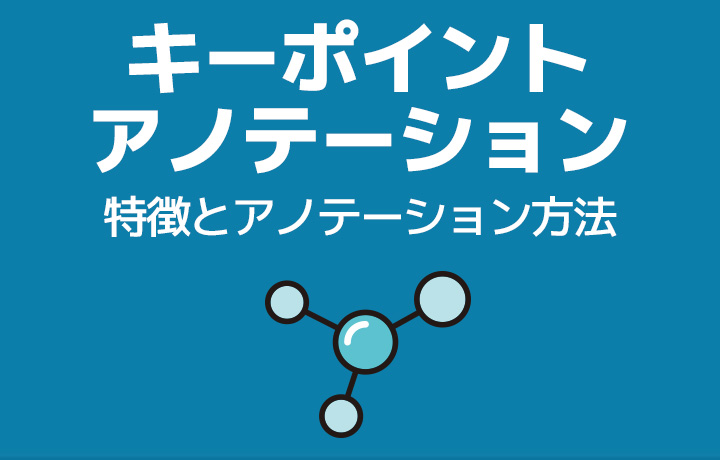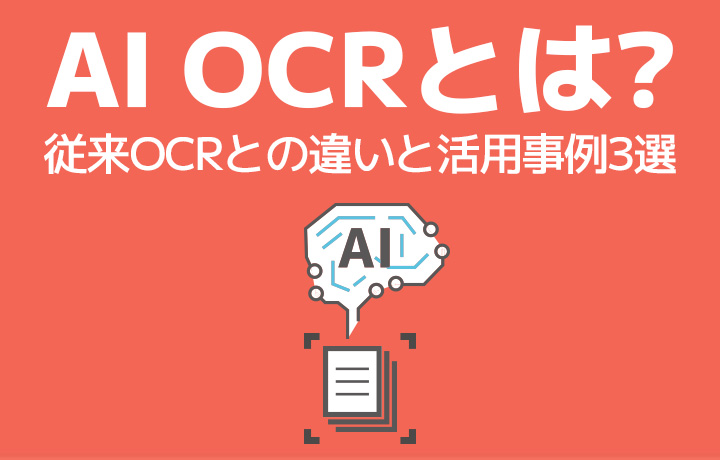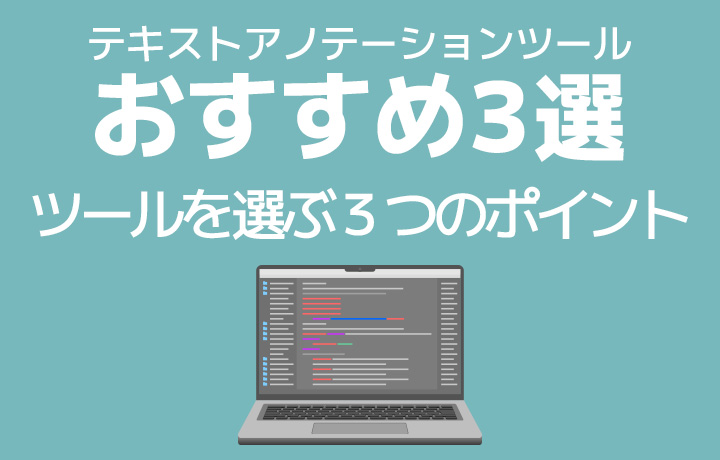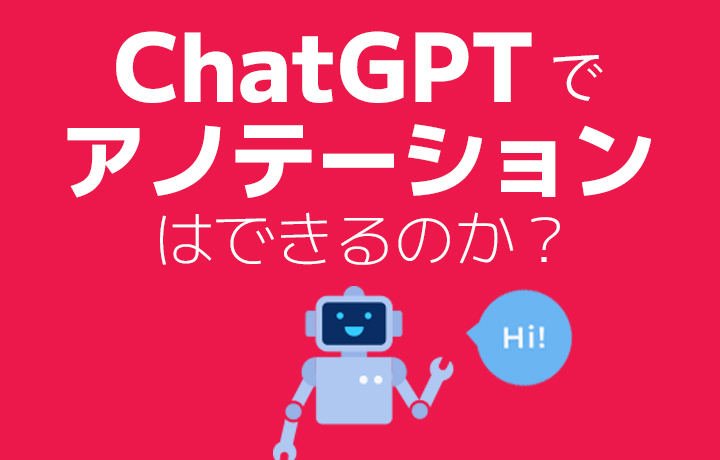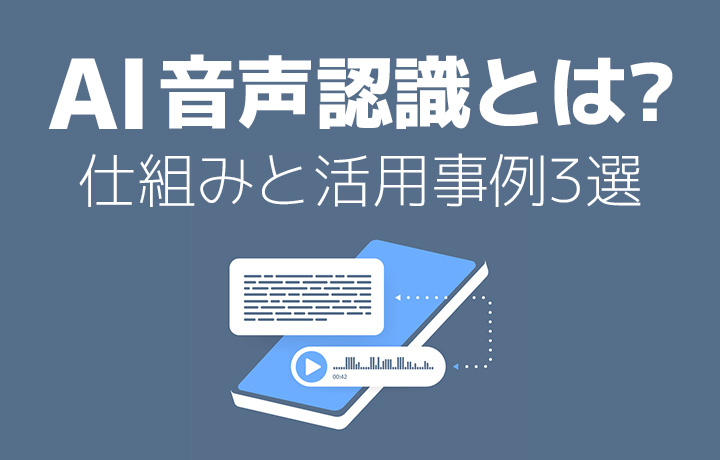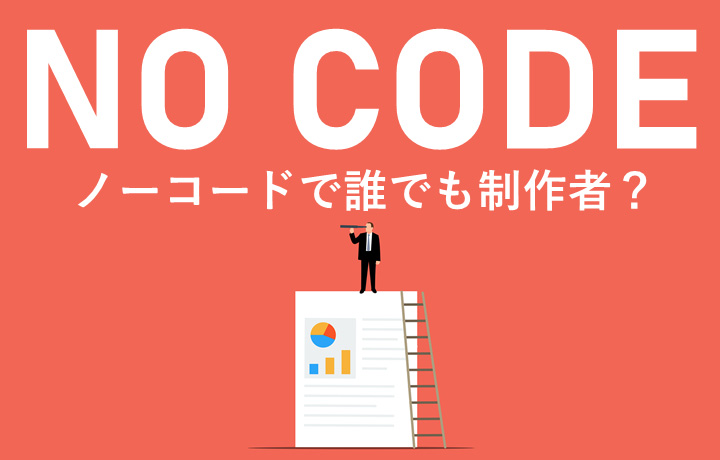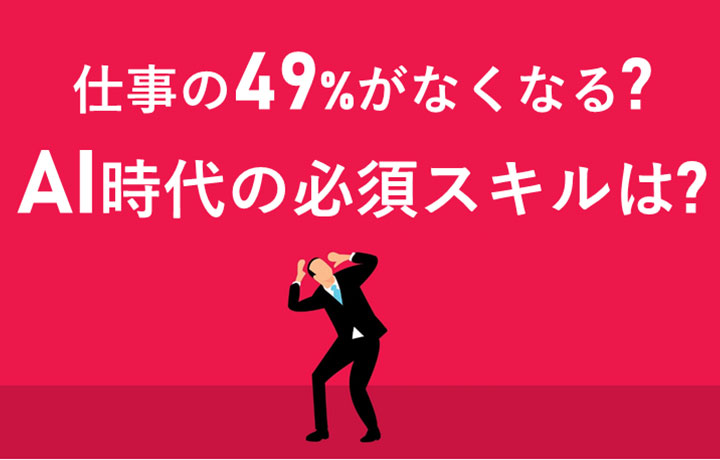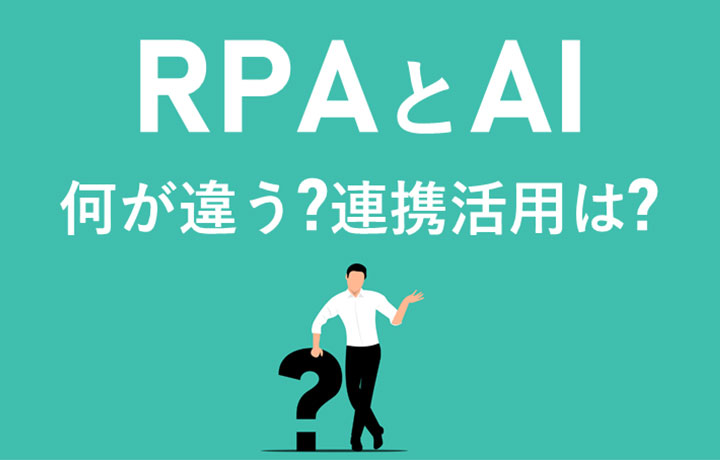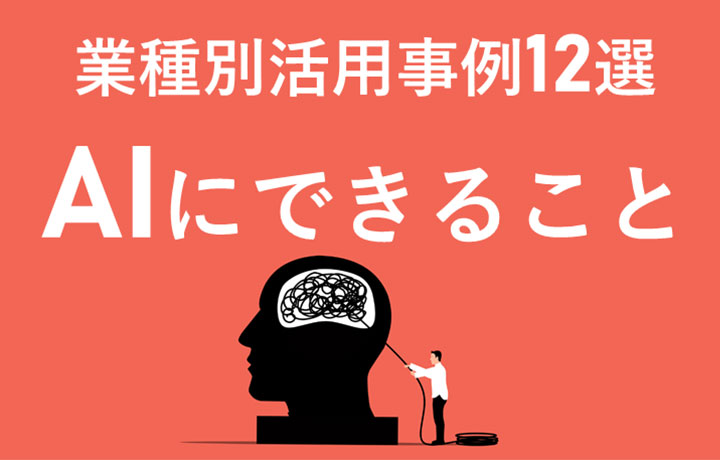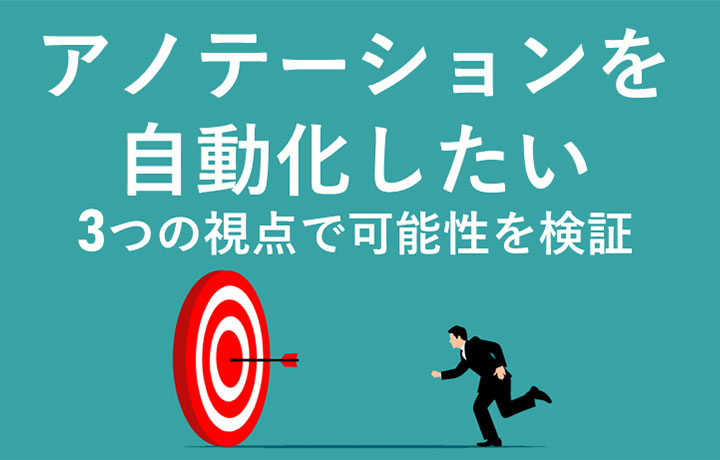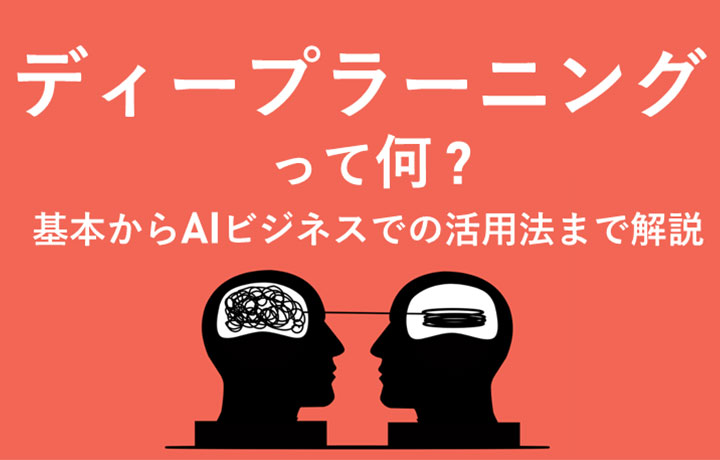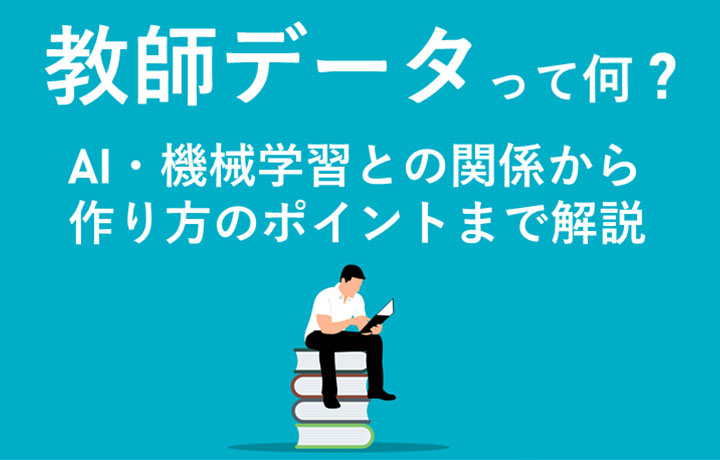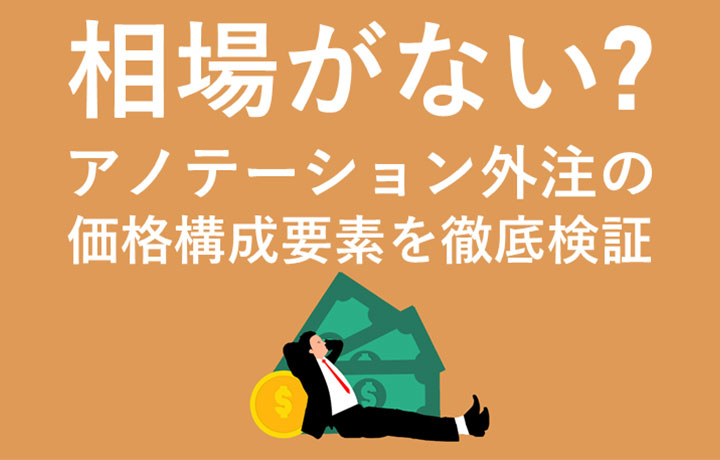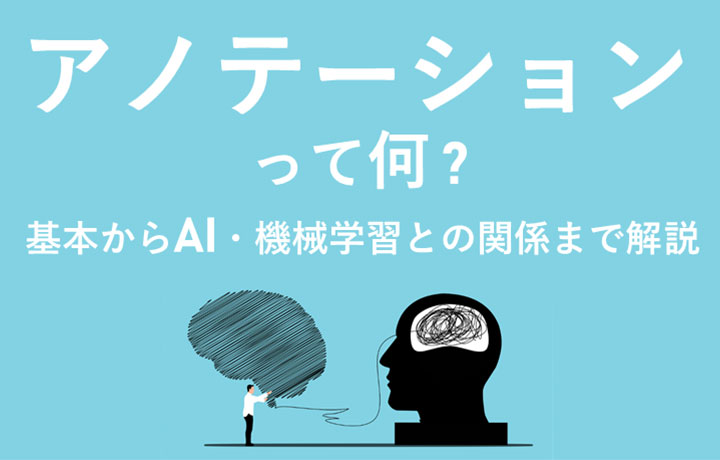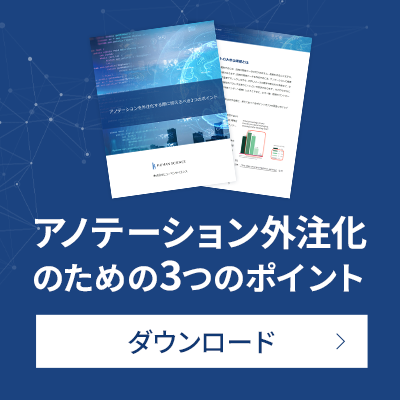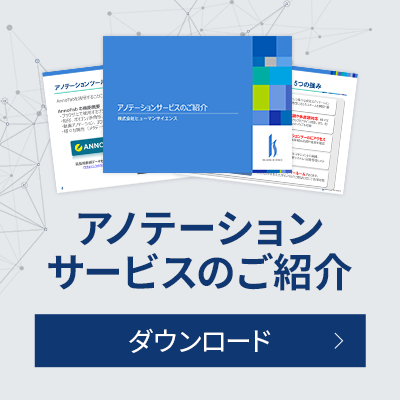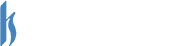スピンオフブログ企画
――DX時代のAIを支えるアノテーション。そのアナログな現場のリアル
ヒューマンサイエンスがクラウドソーシングを使用しないわけ
これまで弊社ではアノテーションやAIに関する様々なブログを発信してきました。そこでは一般的な知識やノウハウを中心にお伝えしてきました。アノテーション作業はその内容を言葉にしてみれば一見簡単なように思えますが、「曖昧性」を多く含んだ「人で行うことが避けられない作業」のため、どうしても人と人の関わりが多くなります。そのため、ある意味泥臭く、巷に溢れるきれいな理屈では済まないことが多く起こり、品質や生産性を確保するためには、実は様々な経験とノウハウが必要になります。
そのため、実際のアノテーションの現場で起こる問題やその対応を具体的に知ることが、アノテーションを成功に導くヒントとして役立つことがあると考えています。
弊社の現場では、実際にどんなことが起こって、具体的にどういった対応や対策をしているか。通常のブログやコラムとは異なり、スピンオフブログ企画と題して、弊社ならではの特徴やこだわりなども含め、リアルな現場の実態をお伝えしたいと思います。
>>過去掲載ブログ(一部)
- 目次
1. クラウドソーシングを活用しないヒューマンサイエンスのアノテーション体制
今更言及するまでもなく、クラウドソーシングはそのメリット・デメリットを理解したうえで、有効に活用すればより効率的なAI開発が行えます。そうした活用のコツについては、これまでのブログで述べてきました。クラウドソーシングの大きなメリットの一つは、短納期・低予算で大量の人材を投入できるということにあります。例えば、数万人のクラウドワーカーから適材適所の人材を確保して、いっきに作業を進めることができたり、多様なデータの収集ができるということは大きなメリットです。
では、弊社でクラウドソーシングを活用しているか、というと、実はそうではありません。
クラウドソーシングを活用することで、確かに得られるメリットは大きいですが、弊社ではあまりその恩恵を受けることが少ないばかりでなく、弊社が仕事を進める中で大切にしていることや、弊社のモノづくりの企業文化に合わないこともあり、直接契約の作業者でアノテーションを行うことが結果的に良いと考えています。弊社では採用時のトライアルを実施し、作業の特性に応じたアノテーターをアサインした体制を構築し、更に作業開始時には案件都度の作業者トレーニングを行っており、またそのことに対してこだわりを持っています。
2. ヒューマンサイエンスがクラウドソーシングを使用しないわけ
すべてに限った話ではないですが、クラウドソーシングのメリットを活用し、大人数の作業で短納期化を図る場合、どうしてもPMと作業者間の密な双方向コミュニケーションによる教育や、作業者の作業に対する理解度の確認が難しくなります。アノテーションは地道に人力で行う作業であるがゆえ、働く人の企業に対するロイヤリティや、モチベーションも品質や生産性を大きく左右します。密なコミュニケーションや親近感から発生するロイヤリティやモチベーションを向上させることが、結果的に品質の安定化や生産性向上に結び付くため、弊社では自社で契約したアノテーターで作業を行う方が良いと考えています。
一部のクラウドソーシングでは安価に人材を確保できることもあるようですが、例えば、時給に換算して最低時給を下回るような状況では、継続的に仕事を続けるモチベーションも下がるでしょうし、欧米では社会問題にもなっていることもあるようです。やはりビジネスにおいて、パートナーの一方に不満や我慢を強いることは、ビジネスの継続性についても疑問符が付きます。
また弊社では特に情報セキュリティの管理体制にご評価をいただき、セキュリティ要件の高い仕事を多く頂いているため、必然的に弊社内のセキュリティルームで作業を行うことが多くなります。やはりテレワークを中心とするクラウソーシングでは、こういったことに対応することがどうしても難しなります。セキュリティ教育の面でも、セキュリティ意識やルールの徹底は、アノテーションツールでの情報漏洩対策やNDA締結だけではどうしても限界があります。そのため作業者への教育や状況に応じた個別の指導が必要になりますが、そういった面でもやはり弊社契約のアノテーターを活用して仕事を進める方が良いと考えています。
3. 人材教育のためのコミュニケーションに対する弊社のこだわり
品質を担保した上で生産性も高める、という相反する目標の両立のために、作業プロセスの改善やアノテーションの自動化のみならず、弊社は「精鋭部隊でのアノテーション作業」「アノテーターの教育を重視」というこだわりを持っております。アノテーションは案件毎に全く異なる仕様・作業内容となります。ただ案件によって仕様や内容が大きく異なっても、アノテーション作業には共通した「アノテーションの勘所」のようなものがあります。これらを養うためには、やはりアノテーターと密にコミュニケーションをとり教育を継続し、経験を重ねることが必要となり、こういった素養が備わってくると、案件毎の作業理解や教育にかかる時間が大きく短縮されます。特に難易度の高いアノテーション作業では、このような素養が高品質・高生産性を確保するために必要となる傾向はさらに強くなります。
このような教育プロセスを一般的に継続的な契約が難しい、と言われているクラウドソーシングで実現するのは困難を伴いますし、直接契約を結び、密な関係をアノテーターと作り上げることで、作業者からの積極的な提案も増え、経験やノウハウが作業者自身のみでなく、PMを介して組織のナレッジとしても蓄積され、結果的に効率的に高い品質と生産性を確保したアノテーションを実現することにつながります。
4. まとめ
ここまで弊社のアノテーターの体制や直接契約のアノテーターによる体制のメリットをお伝えしました。我々は顧客のみならず、パートナーである契約アノテーターの皆さんにも寄り添い、人と人がつながることを大切にしています。これは我々の部署のみならず弊社の企業風土です(これは私がヒューマンサイエンスに転職してきた際に非常に驚いたことでもあります)さらに正直に言うと、やはり人とコミュニケーションを取りながら交流を深め仕事を進めることが純粋に楽しいですし、アノテーターの皆さんから「ヒューマンサイエンスで仕事したい、仕事がやりやすい」と言ってくれることは何より喜びに感じています。とはいえ、時には不本意ながら、お互いに満足できない状況になることもありますし、また人材教育や急な人材確保に多く時間を取られることもあり、効率的な人材確保や短納期化、データ収集のことを考えればクラウドソーシングを活用する方が良かもしれません。加えて弊社の生真面目さがゆえ、人へのフォロー、コミュニケーションや品質の確保に対して時間をかけ過ぎる、と感じることも無くはありません。もちろん効率性を追求することは、忘れてはならない企業の命題の一つでもあり、我々も日々様々な可能性を追求し、研鑽を重ねていますが、自己満足になることなく、企業の良心ともいえる「品質」や「人」を置き去りにせず効率性を追求することを心掛けています。
執筆者:
杦本 和広
アノテーション部 グループマネージャー
・前職Teir1自動車部品メーカーにて、製造ラインの品質設計や品質改善指導を中心に、モデルライン構築のプロジェクトマネジャー、業務効率改善 (リーン改善)コンサルティングチーム等、複数の部門横断プロジェクトを経験。
・現職では、ISO等のマネジメントシステム、ナレッジマネジメント推進等を経て、アノテーション事業の立ち上げ~拡大、アノテーションプロジェクトのマネジメントシステムの構築、改善等のディレクションに従事。
QC検定1級 一般社団法人 品質管理学会会員

 テキストアノテーション
テキストアノテーション 音声アノテーション
音声アノテーション 画像・動画アノテーション
画像・動画アノテーション 生成AI、LLM、RAGデータ構造化
生成AI、LLM、RAGデータ構造化
 AIモデル開発
AIモデル開発 内製化支援
内製化支援 医療業界向け
医療業界向け 自動車業界向け
自動車業界向け IT業界向け
IT業界向け 製造業向け
製造業向け