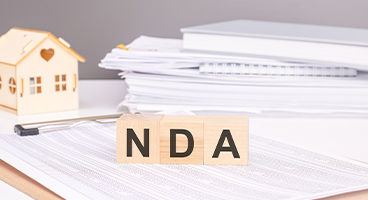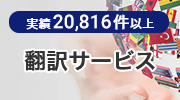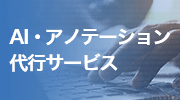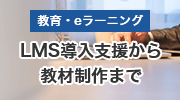AI技術の進歩により機械翻訳の品質は飛躍的に向上しています。近年ではChatGPTに代表される生成AIの登場によって、従来型の機械翻訳エンジンと比べても文脈理解力や表現の自然さで優れた翻訳結果を示すケースが増えてきました。本記事では、OpenAIのGPT-4.1(生成AIモデル)とGoogle翻訳API(v2)を使って日本語の業務マニュアルを翻訳した結果を比較・検証します。翻訳例や具体的な評価ポイントを通じて、生成AI翻訳の実力と課題を探り、生成AIによる翻訳精度が既存の機械翻訳を上回りつつある可能性について考察します。
>>関連記事 翻訳校正とは?高品質な翻訳を実現する方法を徹底解説
- 目次
-
- 1. 比較の概要|生成AI翻訳と既存機械翻訳の条件
- 1-1. 使用したモデルと翻訳条件
- 1-2. 評価の観点
- 2. 翻訳結果の詳細比較|生成AI翻訳と既存機械翻訳の精度検証
- 2-1. 誤訳や訳抜けの有無
- 2-2. 文脈の解釈と省略部分の補完
- 2-3. 記号・番号など形式の正確さ
- 2-4. 文法的な正確さと表現の自然さ
- 3. まとめと考察|生成AI翻訳の精度は既存機械翻訳を超えるか
- 3-1. 他の事例・評価との比較
- 3-2. 生成AI翻訳活用のメリットと留意点
- 3-3. 今後の展望
- 4. AI活用のご相談はヒューマンサイエンスへ
- 4-1. 最新のAI翻訳ツールを積極活用
- 4-2. 豊富な翻訳実績とノウハウ
- 4-3. 自社内にセキュリティルームを完備
1. 比較の概要|生成AI翻訳と既存機械翻訳の条件
1-1. 使用したモデルと翻訳条件
本比較では、以下2種類の翻訳エンジンを使用しました。
OpenAI GPT-4.1(API経由)
OpenAI社が2025年4月にリリースした最新の大規模言語モデルです。生成AIならではの高度な文章生成能力を持ち、文脈理解に基づく自然で柔軟な翻訳が期待できます。
Google翻訳 API v2
Google社提供の従来型のニューラル機械翻訳エンジンです。Web版Google翻訳と同等の翻訳エンジンをAPI経由で利用するもので、高速な応答と安定した品質が特徴です。
日本語で書かれたある業務マニュアルの一部(専門用語や社内略語を含む文章)を英語および中国語(簡体字)に機械翻訳し、その結果を比較しました。原文は一部に主語や目的語の省略、記号「+」での接続など日本語特有の曖昧さを含むため、機械翻訳の実力を試す題材として適しています。
1-2. 評価の観点
翻訳結果の品質を、以下の5つの観点で専門の翻訳者が評価しました。(評価記号:◎=非常に良い、○=良い、△=やや難あり、×=問題あり)
・誤訳・訳抜けの有無:原文の意味を大きく損なう誤訳や、翻訳漏れ(未訳部分)がないか。
・原文省略情報の補完:原文で省略されている主語・目的語や、文脈上必要な情報を適切に補って訳しているか。
・形式の正確さ:箇条書き番号や記号、句読点の扱いなど、体裁面で不自然な点がないか。
・文法的な正確さ:訳文に文法ミスがないか(時制の誤り、構文崩れなど)。
・表現の自然さ:訳文が直訳調に偏らず、読みやすい自然な文章になっているか。
特に原文省略情報の補完や表現の滑らかさは生成AI翻訳の強みとされるポイントであり、注目して評価しました。
2. 翻訳結果の詳細比較|生成AI翻訳と既存機械翻訳の精度検証
上記の評価観点ごとに、OpenAI GPT-4.1とGoogle翻訳APIの訳文を比較します。まず、英語訳・中国語訳それぞれについて総合評価を表にまとめました。
| 評価項目 | OpenAI (英語訳) |
Google (英語訳) |
OpenAI (中国語訳) |
Google (中国語訳) |
|---|---|---|---|---|
| 誤訳・訳抜けの有無 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 原文省略情報の補完 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 形式の正確さ | △ | ✕ | ◎ | ✕ | 文法の正確さ | 〇 | △ | 〇 | △ | 表現の自然さ | △ | △ | △ | ✕ |
※訳文全体を評価した結果。OpenAI(GPT-4.1)の方が概ね高評価で、特に中国語訳では差が顕著。
以下、各観点について具体例を挙げながら解説します。
2-1. 誤訳や訳抜けの有無
⇒重要な情報の伝達精度において、両エンジンとも致命的な誤訳や大きな訳抜けは見られませんでした。原文の大意把握という点では、GPT-4.1とGoogle翻訳の両者ともおおむね良好です。例えば数値データや基本的な事実関係の翻訳は正確で、原文にある内容が欠落することもありませんでした。これは両エンジンの基本性能が高いレベルにあることを示しています。
ただし、細部に目を向けると訳語の選択や固有名詞の処理で若干の差異が認められました。いくつか例を挙げます。
・原文中の役職「店長」は、OpenAI訳では英語で「Store Manager」と適切に訳されました。一方、Google訳は単に「Manager」となり、役職のニュアンスが汎化されてしまいました。細かな意味合いを伝える上ではOpenAIの方が正確です。
・カタカナ表記の固有名詞「ゴールデンラック」について、Googleの中国語訳ではこれが「Golden Rack」と英語のまま残され、訳抜けのような状態になりました。対するOpenAIの中国語訳では「黄金货架」という適切な訳語を選択してくれました。
以上のように、一部ニュアンスの違いこそあれ、文全体の意味を大きく誤解させるような間違いはほとんどありませんでした。ただし専門用語には注意が必要で、場合によっては用語集を用いた事前登録やポストエディットでの修正が求められるでしょう。
2-2. 文脈の解釈と省略部分の補完
⇒文脈理解に基づく補完能力では、GPT-4.1が優れていました。OpenAIは前後関係から原文に明示されない情報を推測し補って訳出するのに対し、Google翻訳は逐語的な訳になり意味が取りにくいケースがありました。
日本語の原文には、主語や目的語が省かれ、「~させ+〇〇」など一見繋がりが曖昧な文があります。こうした部分で両エンジンの挙動を比較します。
・省略された目的語の補完例:
原文:「毎週日曜日に週間数値分析をし、月曜オープンまでに売り場反映させ売上を取れる環境を整える…」
OpenAI訳:「Conduct weekly numerical analysis every Sunday, reflect the results in the sales floor by Monday opening to create an environment that can generate sales,…」
Google訳:「Conduct weekly numerical analysis every Sunday, and reflect the sales floor by Monday opening to create an environment that can generate sales…」
この一文における「売り場反映させ」は、本来「(分析結果を)売り場に反映させ」という意味ですが、目的語「分析結果」が省略されています。OpenAIの訳文では省略された目的語を前後の文脈から推測し、「結果を売り場に反映する」(reflect the results in the sales floor)と補っています。それによって英文の意味がはっきり通るようになりました。一方、Google翻訳では「売り場を反映する」(reflect the sales floorと直訳されてしまい、何を反映するのか不明瞭です。この違いは両エンジンの文脈把握力の差と言えるでしょう。
・記号「+」の扱い:
上記原文の続きになりますが、「…環境を整える+下記マニュアルのチェックで…」という形で「+」記号が文をつないでいます。OpenAI訳ではこの「+」を文脈に応じて「and」に置き換え、一続きの英文として違和感なく接続しました。Google訳では原文同様に「+」をそのまま残したため、英文中に「. +」という不自然な繋ぎが現れています。文章が途切れてしまい、読みにくさを生んでいました。
以上から、GPT-4.1は原文の行間を読んで必要な補足を行う力が高いことが分かります。日本語原文に主語や目的語の省略が多い場合でも、AIが文脈を考慮して滑らかに英文に起こしてくれるのは大きな利点です。一方のGoogle翻訳は、原文に忠実すぎるあまり逐語訳となって意味が通じなくなるリスクがあります。
もっとも、OpenAIの補完も完璧ではありません。例えば中国語訳では、GPT-4.1が省略部分を補おうとしてかえって意味を取り違えた箇所もありました。したがって生成AI翻訳であっても過信は禁物であり、重要な情報が正しく訳出されているか人間による確認は不可欠です。
2-3. 記号・番号など形式の正確さ
⇒翻訳後の体裁面で、OpenAI訳の方は統一感がありました。Google訳は箇条書き番号のブレや句読点の欠落など形式面での不備が散見され、再整形の手間が生じています。
業務マニュアル文書では手順番号や記号の扱いも重要です。今回の比較でも、OpenAI (GPT-4.1) は記号や番号の処理が比較的安定していたのに対し、Google翻訳は形式の不統一が目立ちました。
・箇条書きの番号:原文には「①②③④」のような全角番号が使われていました。OpenAI訳は基本的に番号を引き継ぎましたが、一部で番号自体が消失している項目がありました(例:手順①の英訳で番号が抜けていた)。Google訳では番号は残したものの、形式がバラバラになっています。「①②」の次に突然「3)」という異なる形式が混在し、「4.」とピリオド付きの番号が出るなど、見た目上かなり乱れました。また、番号後のスペース有無も統一されておらず、細部の修正が必要です。
・文頭の大文字・句読点:OpenAI訳では、箇条書き項目の先頭単語がすべて大文字になる現象が見られました(例:「Action」や「Store Manager」など)。英語では文頭以外は小文字で始めるのが通常のため、この点は訳文をそのまま使うには少し手直しが必要です。対するGoogle訳では、逆に文の始まりが小文字のままになっている例がありました。また、英文なのに文末にピリオド(.)が欠落している文もあり、校正が必要です。
・記号類:前述のとおり、OpenAIは「+」を適切に置き換えましたが、Googleは原文の「+」を残してしまいました。他にも括弧や記号の位置など細かい体裁で、OpenAI訳の方が整っています。
以上より、形式面ではOpenAIの訳文の方が最終調整の手間が少ないという評価になりました。しかしOpenAI訳も完璧ではなく、大文字化現象の修正など細部の調整は必要です。一方Google訳はそのままでは体裁がばらつくため、ドキュメントとしてまとめるにはかなり手を入れる必要があるでしょう。
ポイント: 実務でエンジン翻訳結果をドキュメント化する際は、訳文の内容だけでなく体裁面のチェックも重要です。今回GPT-4.1は比較的整った形式を出力しましたが、それでも完全ではありません。自動翻訳を利用する場合、可能であれば翻訳時にスタイル維持機能を使うか、後から見出しや箇条書きの整形を行い、読みやすい最終成果物に仕上げることが大切です。
2-4. 文法的な正確さと表現の自然さ
⇒両エンジンとも基本的な文法は良好ですが、表現の自然さではOpenAI訳の方がやや優れていました。もっとも、原文が長文化して複雑な箇所では両者とも不自然さが残り、ポストエディットが必要です。
・文法の正確さ: GPT-4.1の訳文(英語・中国語とも)には目立つ文法ミスは確認されませんでした。主語と述語の一致や冠詞の用法などもおおむね問題なく、文法的には高い品質です。Google翻訳の英文では、コンマの使い方に起因する文法上の誤り(ランオン・センテンス)が一箇所見られましたが、軽微なもので全体の理解を妨げるほどではありません。文法面だけ見れば、両者とも及第点以上と言えるでしょう。
・表現の自然さ:OpenAI訳文は直訳調を避け、比較的こなれた文章になっていました。例えば先述の「+」を適切に接続詞に置き換えた点や、省略語を補完して訳した点など、読み手を意識した工夫がうかがえます。その結果、読みやすさではOpenAIに分があると感じられました。一方で、原文の構成自体が複雑な部分ではOpenAI訳でも不自然さが残っています。例えば、長い一文に対し、GPT-4.1はセミコロンで区切りつつも一文にまとめて訳しました。この英文は情報過多で少し読みにくく、ここは文章を短く分割する工夫が欲しいところです。
Google翻訳の訳文は、全体にやや機械直訳的な硬さが残る印象でした。特に長い文章ではコンマで繋ぎすぎて構造が破綻気味になり、冗長で読みにくい訳になっていました。中国語訳でも「销售领域」(売り場の不自然な訳)や「与服装协调」(コーディネートの不自然な直訳)などが見られ、ネイティブには違和感のある表現が散見されます。総じて、ポストエディットの負荷はGoogle訳の方が大きいと感じました。
このように、短文・平易な文ではGPT-4.1が非常に流暢な訳を出すのに対し、長文化すると両エンジンとも調整が必要という結果でした。「そのまま使える訳文」の割合はOpenAIの方が多かったものの、最終的な品質確保には人間の手による校正・リライトが重要です。
5つのポイントは?

3. まとめと考察|生成AI翻訳の精度は既存機械翻訳を超えるか
ここまでの比較から、OpenAI GPT-4.1翻訳は総合的にGoogle翻訳APIより質が高いという結果になりました。特に「省略補完」「形式統一」「表現の滑らかさ」でGPT-4.1が優れていました。一方で両者とも実務利用にはポストエディットが不可欠であり、完全自動で高品質な翻訳が得られるわけではない点には注意が必要です。
以下では、他の事例も踏まえた現在の翻訳エンジンの位置づけや、生成AI翻訳を活用する上でのメリット・留意点、そして今後の展望について考察します。
3-1. 他の事例・評価との比較
今回のケース以外でも、近年はChatGPT(GPT-4)の翻訳力がGoogle翻訳を上回るとの報告が増えています。例えば社内の別テストでは、GPT-4.1がDeepLを含めた複数の翻訳エンジンと比較しても遜色ないか、それ以上の正確さを示す場面が確認されています。実際、ある難解な英文の翻訳ではGPT-4.1だけが原文の意味を正確に捉えたというケースもありました(DeepLや他モデルは一部誤訳・訳漏れが発生)。このように最新のGPTモデルは既存トップクラスの翻訳エンジンと肩を並べる品質を発揮し始めています。
一方、第三者の評価では依然としてDeepLが高評価を得る例もあります。外部の翻訳比較では「DeepL > ChatGPT > Google翻訳」といった順位付けがされることもあり、分野や言語によって得意・不得意があるようです。ただ、ChatGPT系モデルはプロンプト指示で品質向上が可能な点が特徴です。例えば用語や文体の指示を与えることで格段に精度が上がるケースが報告されています。「翻訳は『指示』で進化する」という指摘がある通り、使い方次第で性能を引き出せるのが生成AI翻訳のユニークな点です。
総じて、生成AI翻訳が既存の機械翻訳エンジンに追いつきつつあるのは間違いありません。特に日本語のように文脈依存が大きい言語では、文脈理解型のGPTモデルが強みを発揮しやすいと言えるでしょう。
【参考ブログ】
>OpenAI新モデルGPT-4.1の翻訳精度は?DeepLと比較検証!
>ChatGPTとDeepL②:製造業・IT分野の日英翻訳精度比較― 翻訳は「指示」で進化する?精度比較と改善方法を徹底検証
3-2. 生成AI翻訳活用のメリットと留意点較
メリット: 生成AIモデル(GPT-4.1等)の翻訳最大の強みは、文脈やニュアンスを汲み取った柔軟な訳出にあります。従来エンジンでは逐語訳になりがちだった箇所も、ChatGPTなら内容に即した言い換えや、必要情報の補完をしてくれます。またスタイルの調整が容易なのも魅力です。カジュアル/フォーマルなどトーンの指定や、専門用語を使う/避けるといった細かな指示ができ、その通りに反映されるため、目的に合った翻訳文を得やすいのです。さらに翻訳以外にも、要約や校正、用語集作成などの関連タスクを同じモデルでこなせるため、翻訳プロセス全体のDX(デジタル変革)に寄与するポテンシャルがあります。実際、生成AIの導入によって翻訳工程の大幅な効率化が実現した例も報告されています。
留意点: 一方で、生成AIにはハルシネーション(幻覚)と呼ばれる問題があります。つまり、原文にない内容をそれらしく生成してしまうリスクです。今回のテストでは大きなハルシネーションは見られませんでしたが、過去にはChatGPTが翻訳時に勝手に補足説明を書き加えてしまったケースなどもあります。特に数値や固有名詞の扱いには注意が必要で、重要なデータは翻訳後にクロスチェックした方が安全です。また、生成AIは同じ入力でも応答が一定しないことがあります。バージョンアップやその時の内部状態で訳が微妙に変わる可能性があるため、ドキュメント全体で用語や文体を厳密に統一するには工夫が要るでしょう(必要なら用語固定のルールをプロンプトに与える等)。
加えて、利用コストや制約も考慮すべきです。API経由でGPT-4を使う場合、文字数に応じた料金が発生します。また処理時間も従来エンジンより長く、大量文書の即時翻訳には不向きです。そして情報セキュリティの観点では、入力した社内文書データが外部AIサービスに渡る点に敏感になる必要があります。機密情報を扱う際は、必ず業務向けの有料APIを利用し、データが学習に使われない契約を結ぶことが重要です(無料のChatGPTウェブ版で社内文書を翻訳するのは避けましょう)。
以上を踏まえ、生成AI翻訳は強力なツールである反面、正しく使いこなす知見が求められると言えます。
3-3. 今後の展望
今回の比較では、生成AI翻訳(GPT-4.1)の高い性能を実感できました。今後、この傾向はさらに強まると予想されます。OpenAIやGoogleはもちろん、各社から新たな高性能言語モデルが続々と登場しています。2023年末に発表されたGoogleの新モデルGeminiも多言語対応が注目されており、競争は激化しています。
もっとも、現段階で完璧な翻訳が自動で得られるわけではなく、人間の関与は依然重要です。OpenAI・Googleいずれの訳文もポストエディットやリライトによって初めて実用文書として完成する状態でした。生成AIの台頭により「翻訳者の仕事が不要になる」のではなく、むしろ翻訳者が高度なレビュー・編集によって最終品質を保証する役割が一層求められるでしょう。今回の比較からも、AIと人間の協業による効率化の可能性を強く感じました。
まとめ: 生成AI翻訳はまだ発展途上とはいえ、その実力は既存の翻訳エンジンに匹敵しつつあります。上手に活用すれば、翻訳業務の飛躍的な効率化も夢ではありません。一方で、現時点ではAIだけによる高品質翻訳は難しいのも事実です。だからこそ、人間とAIのハイブリッド翻訳でお互いの長所を活かし合うことが大切です。皆様もぜひ最新の翻訳AIを試し、その可能性と限界を体感してみてください。
4. AI活用のご相談はヒューマンサイエンスへ
翻訳AIをはじめとする最新テクノロジーの活用について、「どう導入すればいい?」「うちの文書にも使える?」といったお悩みがありましたら、ぜひヒューマンサイエンスにご相談ください。当社は長年にわたり業務翻訳を支援してきた実績から、AI翻訳ツールの導入や運用支援まで幅広くサポートいたします。以下に当社サービスの特徴を紹介します。
4-1. 最新のAI翻訳ツールを積極活用
ヒューマンサイエンスでは、専門用語の多い業務文書でも、AI翻訳+翻訳メモリ技術を組み合わせることで高精度かつ高速な翻訳を実現します。お客様のニーズに合わせて最適なエンジンを選定し、効果的に活用します。
また、ChatGPT (GPT-4.1)やDeepLをはじめとする最新AIエンジンを組み込んだ自社開発ツール「MTrans」シリーズも提供しています。
>>ヒューマンサイエンスのAI翻訳ツール提供サービス4-2. 豊富な翻訳実績とノウハウ
1985年の創業以来、マニュアル翻訳やIT・医療分野の専門翻訳など35年以上の実績があります。経験豊富なスタッフが、翻訳プロセスや品質管理のノウハウを駆使し、AI翻訳の活用についても最適なアドバイスを行います。「AI×人間」のハイブリッド翻訳体制で、多くのお客様の業務効率化に貢献してきました。
>>ヒューマンサイエンスの翻訳サービス4-3. 自社内にセキュリティルームを完備
機密性の高い文書でも安全にご依頼いただけるよう、社内にセキュリティルームを設置し万全の情報管理を行っています。翻訳データはお客様ごとの専用データベースで扱い、第三者に漏洩しない環境を整備しています。AI翻訳エンジンの利用においても、API経由で行うことでデータが外部に蓄積されるリスクを排除しています。
>>ヒューマンサイエンスの情報管理
当社では上記のように、お客様のニーズに合わせた最適な翻訳ソリューションをご提案できます。「まずは話を聞いてみたい」という段階でも構いません。AI翻訳の導入支援から専門分野の翻訳代行まで、お気軽にヒューマンサイエンスにお問い合わせください!
5つのポイントは?