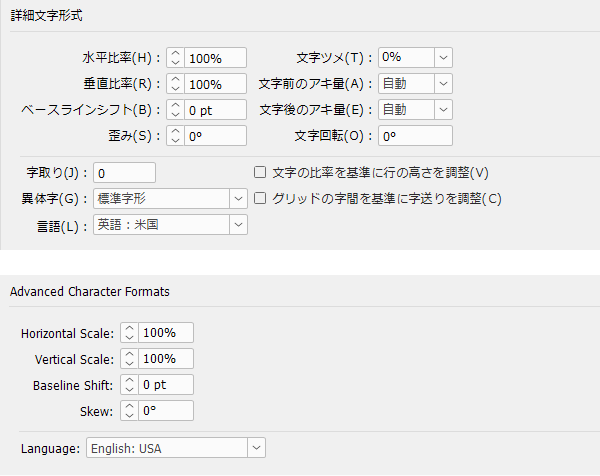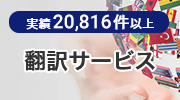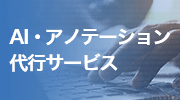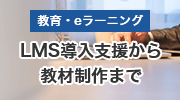先日、弊社で開催したオープンセミナーでは、 個人の翻訳者様にもご参加いただきました。
翻訳関連の機関紙などでも、機械翻訳や、機械翻訳後の修正を行う「ポストエディット」が
とりあげられることも 多くなってきています。
やはり、個人の翻訳者の方々も、
機械翻訳とこれからどうやって向き合っていくべきなのか気になっているようです。
では、「翻訳者」と「ポストエディター」は、どんな点が異なるのでしょうか?
今回は、そのポイントについて、少しだけ触れてみたいと思います。
●ベースになる「翻訳の力」は基本的に同じ
「ポストエディットは、翻訳者になる前の学生なんかにやらせているのでは?」
という声を聞くこともありますが、ヒューマンサイエンスとしては、
やはりポストエディットも「プロフェッショナル」が行うべき、と考えています。
機械翻訳のポストエディットは、「ベースになる翻訳があって、それを修正していくだけ」
というイメージから、学生でもできるのでは、という考えに至るようですが、
実際には、機械翻訳エンジンは、思わぬ誤訳をしてしまったり、
適切な専門用語が使用できなかったりします。
また、似たような用語がある場合に、文脈によって訳語を適切に使い分ける、
というのも、あまり得意とはしていません。
そうした翻訳のミスに気がつく力、というのは、
やはり長年の翻訳の経験によって培われた「翻訳の力」がベースになると言えるでしょう。
●小さなミスに気がつく「目ざとさ」
ベースとなる翻訳の力に加えて特に重要なのが、「目ざとさ」といえるでしょう。
機械翻訳でよくあることとして、「一見するときちんと訳されているのに、
よく読むと意味が正しく反映されていない」ということがあります。
例えば、三単現の s が抜けている、時制が誤っている、など。
時には、原文は否定文なのに、訳文では “not” が抜けてしまって、
結果として意味がまったく逆になっている、ということもあります。
こうした訳文は、一見すると違和感なく読めてしまうし、
意味としても(それが逆の意味であっても)成り立ってはいるため、
丁寧に見ていかないとつい見落としてしまいがちです。
「ポストエディット」においては、こうしたミスに気がつく「目ざとさ」は、
イチから自分で訳文を作り上げている「翻訳」において以上に必要とされるでしょう。
●まとめ
このほかにも、「ポストエディター」に求められる能力で、
「翻訳者」と異なる点がいくつかあります。
気になる方は、是非お問い合わせください。
翻訳者の方々は、これからポストエディットの依頼がされることも
多くなってくると思います。
機械翻訳を「自分たちの仕事を奪う脅威」とだけ捉えるのではなく、
これからの時代を担っていく重要なツールの1つとして考え、
ポストエディットの作業などにも積極的に向き合うことによって、
自分たちの仕事の幅を広げる1つの手段にもなるのではないでしょうか。
ヒューマンサイエンスでは、翻訳やポストエディットの作業をお願いできる
フリーランス翻訳者の方を随時募集しております。
是非、ご応募ください。
また、社内の翻訳者やポストエディターをどのように育てたらよいか迷っている、
というクライアント企業の方からのお問い合わせも、お待ちしております。
出張セミナーなども実施していますので、是非お声かけください。
関連サービス
ポストエディット支援ツール MTrans Post-Edit Booster
機械翻訳特有のミスを自動的に修正してポストエディット作業を効率化!
機械翻訳セミナー開催予定
機械翻訳セミナーは毎月開催しております。

訳文エラーとポストエディット
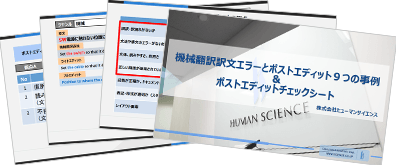
関連記事
【ノウハウ】品質、どこまで求める?ポストエディットの設計基準
【ノウハウ】ポストエディットの国際規格(ISO 18587)
【ノウハウ】ポストエディットでの修正観点は?