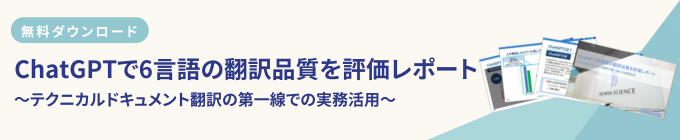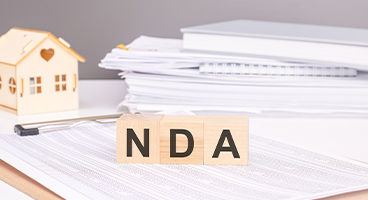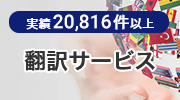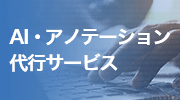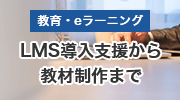- 目次
1. 背景と課題:生成AIで翻訳評価は可能か?
“ChatGPTなどの生成AIで翻訳品質チェックを自動化できないか?” 近年この問いが注目を集めています。翻訳現場からは例えば次のような声が聞かれます。
・「翻訳の品質を人手で確認するのは大変だ」
・「多言語対応が求められているが、評価できる人材がいない」
マニュアルや技術文書の多言語翻訳が当たり前になる中、自社内で迅速かつ客観的に翻訳品質を評価したいというニーズは高まっています。しかし、人手によるチェックは言語数が増えるほど時間・コスト面の負担が大きく、評価者の主観ブレも避けられません。
そこで期待されるのがChatGPTをはじめとする生成AIの活用です。「AIならば一貫した基準で自動評価してくれるのでは?」という発想です。もしChatGPTで翻訳チェックが完結すれば、納品翻訳の品質を即座に判断し、必要に応じて外部専門家への再依頼箇所を絞り込むことも可能になるでしょう。
もっとも、生成AIに評価を任せることには懸念事項もあります。
例えば:
・意図した通りの指摘が得られるか?(プロンプト次第で結果が変わりすぎないか)
・機密文書でも安全に使えるか?(入力データが外部に漏洩・学習利用されないか)
・人間並みに正確に評価できるか?(過不足なく誤りを検出できるか)
こうした課題に答えるべく、ヒューマンサイエンスではChatGPTによる翻訳品質評価の有用性を検証する社内セミナーを実施しました。本記事では、その概要と結果をご紹介します。
2. 検証設計:ChatGPTによる翻訳評価の方法
まず、ChatGPTによる多言語翻訳チェックの検証方法を説明します。今回は技術文書の英語原文とその多言語訳を用い、ChatGPT (GPT-4)の評価とプロの翻訳者による評価を比較しました。

・対象データ:英語の技術マニュアルをフランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・ロシア語・オランダ語に翻訳した対訳データ(各言語 約200文、約1,000ワード)
・評価手法:上記6言語について、専門翻訳者2名による品質評価結果と、**ChatGPT (GPT-4, 2024年7月時点)**による評価結果を収集し比較
・使用ツール:当社開発の翻訳QAツール「HS XChecker」に組み込んだLLM校正機能を使用。対訳データを1文ごとにChatGPTに読み込ませ、自動で校正・評価させました。
評価観点は一般的な翻訳品質基準に沿い、以下の5項目です。
①誤訳・訳漏れ(原文の意味が正しく訳出されているか)
②文法エラー(訳文として文法的に誤りがないか)
③形式エラー(用語統一や表記ゆれ、記号の使い方など形式面の誤り)
④不自然な表現(訳文として不自然・分かりづらい表現になっていないか)
⑤不適切な表現(文脈や読者にそぐわない言葉遣いになっていないか)
以上の「正確さ」と「流暢さ」の観点で、ChatGPTが各種エラーをどこまで検出できるか、人間の評価と突き合わせて分析しました。
3. 結果:生成AIの翻訳評価の傾向と限界
結論として、ChatGPTのみで完璧に翻訳チェックを完結させることは難しいというのが検証結果です。ただし、エラーの種類によっては高精度で検出できる項目もあり、工夫次第で有用な補助ツールとなり得ることも分かりました。以下は評価観点ごとの精度と傾向のまとめです。
| 評価観点 | ChatGPTの精度 | コメント |
|---|---|---|
| 文法エラー | ○(高精度) | 文法ミスの検出は比較的正確に可能 |
| 誤訳・訳漏れ | △ (一部検出可能) | 重大な誤りは捉えるが、不要な指摘も多い |
| 形式エラー | × (検出困難) | 括弧の種類違い等、形式面のミスは見落とし |
| 不自然な表現 | × (検出困難) | ニュアンス評価が苦手でほとんど検出できず |
| 不適切な表現 | × (検出困難) | 文脈理解が不十分でほとんど検出できず |
(※「◎」非常に精度高、「△」一部は検出できるが限界あり、「×」検出は難しい傾向)
上表の通り、ChatGPTは「文法エラー」検出が得意で、人間の指摘とほぼ一致する結果を示しました。例えばロシア語訳での代名詞の性別一致ミスなど、文法違反となるケースは的確に捕捉できています。また「誤訳・訳漏れ」についても、完全に意味が抜けてしまっている訳漏れや明らかな誤訳は概ね検出できました。
しかし「誤訳・訳漏れ」では、人間から見て許容範囲の訳に対して過剰に誤り判定するケースが散見されました。例えば英語の章タイトル“Read This First”に対するスペイン語訳「Leer antes de empezar」に対し、ChatGPTは「’This’に相当する語が訳文にない」と指摘しましたが、実際にはスペイン語として自然な訳で誤訳ではありません。このように、本来問題ない表現を誤検出してしまうことがある点には注意が必要です。
一方、「形式エラー」(記号や表記の統一ルール逸脱)や「不自然/不適切な表現」の検出は出来ない傾向にありました。例えばフランス語訳で引用符の種類が不適切なケースでは、人間の評価者からの指摘はありましたがChatGPTは見逃しました。またドイツ語訳でサービス名を指す代名詞の使い方が文脈に合っていない例でも、ChatGPTは検出できませんでした。これらは各言語固有の細かな表現ニュアンスやスタイル規則に関わる部分であり、現状のChatGPTの限界が現れたと言えます。
以上より、今回の検証では「ChatGPTだけでは翻訳チェックは完遂できない」という結論に至りました。ただし、文法ミスのように機械的チェックが有効な観点では人間に近い精度で役立つことも事実です。重要なのは、得意な部分はAIに任せつつ、苦手な部分は人間が補うという使い分けでしょう。
4. 改善策:ハイブリッド運用で評価精度を高める
ChatGPTの限界を踏まえ、ヒューマンサイエンスではAIと人間のハイブリッドによる翻訳チェック手法を模索しています。その鍵となるのが、当社独自開発の「HS XChecker」と「LLM校正ツール」の組み合わせです。
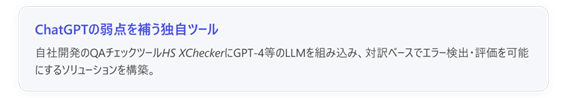
HS XCheckerは従来、翻訳物の用語統一や数値・書式のチェックなどを行うQA検証ツールですが、ここにOpenAIのGPTエンジンを連携させた「LLM校正支援機能」を開発しました。具体的には、原文と訳文の対訳を1文ずつ解析し、上記5観点のエラーを自動検出・表示する機能です。
この仕組みにより、ChatGPTをそのまま使う場合に指摘された懸念点(全体を一度に解析すると代表例しか出ない、勝手に存在しない誤りを産出する等)を克服しています。エラーは原文訳文ペアごとに一覧表形式で可視化されるため、どの文のどこに問題があるかが一目瞭然です。人間のレビュー担当者はChatGPTの指摘をベースに、本当に問題かどうかを取捨選択していくだけで済み、大幅な効率化につながります。
また、セキュリティ面でも安心して使える設計です。ツールではOpenAIのAPIを利用しており、解析に用いた対訳データがモデルの学習に再利用されることはありません。
生成AIの力を借りつつ最終判断は人間が行う「ハイブリッド運用」が、現時点で最も現実的かつ有効な解決策だと感じています。
5. 今後の展望と活用可能性:AI時代の翻訳評価はどう進化するか?
今回の検証から、AIによる翻訳評価の「現在地」と「これから」が見えてきました。最後に、得られた知見と今後の展望をまとめます。
・AI評価はあくまで補助ツール:
ChatGPT単独ですべての誤りを網羅することはできず、細かなニュアンスや文脈判断は人間の目が欠かせないと分かりました。同時に、文法チェックなど定型的な部分はAIが十分こなせます。「得意:AI、苦手:人間」が賢い役割分担になります。
評価プロセスの効率化:
生成AI時代の翻訳チェックは、全面的な自動化ではなく、人間との協調による効率化が主流になるでしょう。AIの指摘を前提情報として、人間がより創造的・高次の判断に注力する形です。今回明らかになったAIの得意不得意を踏まえ、各社のワークフローでも最適なハイブリッド運用の設計が鍵となります。
更なる可能性:言語拡大や専門分野への応用:
GPT-4は数十の言語を扱えるため、今回対象とした欧州言語以外にも評価対象を広げることができます。また将来的には、法務文書や医療文書といった専門分野での品質チェックにも応用できる潜在性があります。専門性の高い領域では、AIの判断を鵜呑みにするのは危険ですが、一定のパターン検出や初期チェックにはAIを活かし、最終判断は専門家が行うという形であれば十分役立つでしょう。当社でも、こうした分野別の検証や評価精度の向上策を継続研究し、サービスに反映していく予定です。
以上のように、翻訳評価へのAI導入は「人間を代替する」ものではなく「人間を支援する」形で進化すると考えられます。品質要求を満たしつつ業務効率も向上できるよう、皆様もぜひAIと人間のハイブリッド評価を取り入れてみてはいかがでしょうか。
6. 検証の詳細資料は無料でダウンロードいただけます!
今回ご紹介した内容は一部です。ChatGPTを用いた翻訳評価の詳しい検証結果をまとめた無料レポートをご用意しています。実際の評価データに基づくグラフや具体的な指摘例も多数掲載しておりますので、興味のある方はぜひご一読ください。
また、翻訳業務での生成AI活用に関するご相談事項についても承っています。要件が固まっていない段階でもお気軽にお問い合わせください。
>>お問い合わせはこちらから
ぜひダウンロードとあわせてご活用いただき、今後の業務改善にお役立てください。