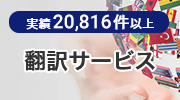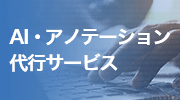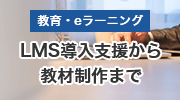今回は、以前のブログ「IT・FA分野の翻訳でよくある間違い③ ~主語はユーザーか、システムか?表内の説明文の正しい翻訳方法~」で紹介した内容に関連します。
前述のブログでの要点をおさらいしましょう。
機能・処理・操作・フローなどの説明文において・・・
・ユーザー側で操作するもの → 命令形を使う
例:
移行したいモードの設定値を設定します。
Set a setting value for the mode to be switched.
(「設定する」は、システム側の処理ではなくユーザーの操作なので、命令形の「Set」を使う。)
・システム側で処理するもの → 三単現を使う
例:
設定された周期で低速サイクリック伝送を行います。
Performs low speed cyclic transmission at the set period.
(「伝送を行う」は、ユーザーの操作ではなくシステム側の処理なので、三単現「Performs」を使う。)
しかし、機械翻訳は、「設定」・「設定する」・「設定します」といった動詞が、ユーザー側の操作なのか、システム側の処理なのかを区別できず、命令形で統一するケースが多いです。
そのため、ポストエディットの際に注意を払う必要があります。
例文で見ていきましょう。
>>関連DL資料:機械翻訳訳文エラーとポストエディット9つの事例&ポストエディットチェックシート
- 目次
-
1. システム側の処理
- ■原文
- インストーラでは以下の処理が行なわれます。
- • インストール先環境(OS)設定の確認
- • 必要なファイルのコピー
- • サービス化のためのシンボリックリンク作成
- ■機械翻訳
- The installer does the following:
- • Check the installation environment (OS) settings
- • Copy required files
- • Create symbolic links for service
- ■修正後
- The installer performs the following processes.
- • Confirms the installation environment (OS) settings.
- • Copies the required files.
- • Creates a symbolic link before installing it as a service.
インストーラの処理(機能)についての説明文なので、命令形は不適切です。
従って、三単現を使い、システム側にあるインストーラが行う処理であることを明確にします。
(👉ポストエディットのポイント:原文のピリオド有無にかかわらず、訳文では、命令形や三単現で始まる表現は完全文章として扱い、最後にピリオドをつけるのがおすすめです。)
もう一つの例を見ていきましょう。
2. システム側の機能
- ■原文
- 統合画面機能では、以下の機能を提供します。
- • 各種の運用管理画面を統合的に表示する
- • 画面レイアウトをカスタマイズする
- • カスタマイズした画面レイアウトを保存・復元する
- ■機械翻訳
- The integrated screen function provides the following functions.
- • Display various operation management screens in an integrated manner
- • Customize the screen layout
- • Save and restore customized screen layouts
- ■修正後
- The integrated screen function performs the following.
- • Displays various operation management screens in an integrated manner.
- • Customizes the screen layout.
- • Saves/restores a customized screen layout.
前の例と同様に、表示・カスタマイズ・保存・復元するのは、ユーザーではなく、システム側にある統合画面機能なので、命令形を全て三単現に変える必要があります。
(👉ポストエディットのポイント:「統合画面機能では、以下の機能を提供します。」→「The integrated screen function provides the following functions.」は、特に問題ないですが、原文が冗長なので、読みやすく「統合画面機能は以下を実行します。」の意味になるように訳文を変えました。)
システム側で処理するものについて、状況によっては、三単現ではなく、違う文法や構成を使う場合もあります。該当する例を見ていきましょう。
3. 機能の処理フロー
- ■原文
- パケットキャプチャ監視の処理フローは、以下の通りになります。
- 1. 監視設定を登録
- 2. 対象ノードに存在するすべてのネットワークカードからパケットを取得
- 3. 指定のパケット数が溜まったらダンプファイルを出力
- 4. 出力されたダンプファイルに対して監視・収集処理を実行
- ■機械翻訳
- The processing flow of packet capture monitoring is as follows.
- 1. Register monitoring settings
- 2. Get packets from all network cards on the target node
- 3. Output a dump file when the specified number of packets is accumulated
- 4. Execute monitoring / collection processing for the output dump file
- ■修正後
- The process flow of Packet Capture Monitor is as follows.
- 1. The monitor setting is registered.
- 2. Packets are collected from all network cards existing on the target node.
- 3. A dump file is output when number of packets reach the specified amount.
- 4. Monitoring and data collection are executed for the output dump file.
機能の説明ではなく、処理フローの説明です。よって、動詞の対象を主語として前に持ってきて、第5文型のいずれかの構成を使うと自然です。
今回紹介したエラーは、人手翻訳と機械翻訳の両方でよく見かけます。
このようなエラーは、読む側が混乱するおそれがあるため、文脈に応じてどの文法が適切なのかを把握し、適切に修正する必要があります。
個人的な意見ですが、これから(ニューラル)機械翻訳の品質がどれだけ上がっても、ある動詞に対し、機械翻訳がシステム側の処理なのか、ユーザー側の操作なのかを的確に区別し、正しい訳文を生成できるようになるのは難しいと思います。
そのため、このようなエラーの対応は、技術資料や操作マニュアルなどのポストエディットの作業において欠かせないと思います。
>>関連DL資料:機械翻訳訳文エラーとポストエディット9つの事例&ポストエディットチェックシート