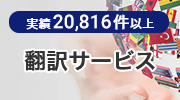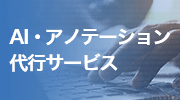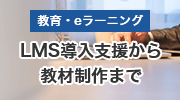「whose」には、名詞を修飾する関係代名詞としての使い方と、疑問代名詞としての使い方があります。まず、疑問代名詞としての使い方は比較的分かりやすく、「Whose bag is this?(これは誰のカバンですか?)」のようにシンプルに使われます。
一方、名詞を修飾する関係代名詞としての「whose」を正しく使うのは意外と難しく、知らない人も多いかもしれません。特に、ITやFA分野の日英翻訳では「whose」を使う場面が比較的多いため、使い方に慣れておくと非常に役立ちます。
今回は、具体的な例をいくつか紹介しながら、関係代名詞「whose」の正しい使い方と、間違えやすいポイントについて説明します。
- 目次
5つのポイントとは?

1. 「whose」におけるよくある間違い①:「whose」を使うべきところで前置詞句を使う
| 原文 | 弊社では、お納めした製品の保証期間が過ぎたものにつきまして、保守点検を有償にて承っております。 |
|---|---|
| 訳文(修正前) | For a fee, we provide maintenance and inspection services for delivered products with its warranty period expired. |
「with its warranty period expired」という表現では、「its」がどの製品を指すのか不明確になり、文章が冗長で不自然になります。また、この構造は英語としても理解しづらくなります。正しく修正すると、以下のようになります。
| 訳文(修正後) | For a fee, we provide maintenance and inspection services for delivered products whose warranty period has expired. |
|---|
「whose」を使うことで、納品された製品とその保証期間との関係が明確になり、文章がシンプルで流れが良くなります。関係代名詞「whose」は、所有や関係を表すために適切に使われており、この表現では無駄な要素が省かれ、簡潔で読みやすい文章になります。
2. 「whose」におけるよくある間違い②:「whose」を使うべきところで「前置詞+which」を使う
| 原文 | Route History画面で、詳細を確認したいRecordをタップします。 |
|---|---|
| 訳文(修正前) | On the Route History screen, tap the Record for which you want to check the details. |
この表現では、「for which」によって「Record」と「details」の関係を示していますが、冗長で分かりにくい構造になっています。前置詞「for」と関係代名詞「which」を組み合わせることで、文が硬く不自然に感じられます。正しく修正すると、以下のようになります。
| 訳文(修正後) | On the Route History screen, tap the Record whose details you want to check. |
|---|
「whose」を使うことで、「Record」と「details」の関係が直接示され、文がより簡潔で自然になります。
3. 「whose」におけるよくある間違い③:「whose」を使うべきところに関係副詞を使う
| 原文 | X線高電圧発生装置とX線高電圧発生装置から電源が供給される構成品の電源を入れるスイッチです。 |
|---|---|
| 訳文(修正前) | This switch turns on the power of the X-ray high voltage generator and the components where power is supplied from the X-ray high voltage generator. |
「where」は場所を示す関係副詞で、通常は物理的な場所や位置に使います。この場合、場所ではなく「電源が供給される」という関係を表現したいので、「where」を使うのは不適切です。
| 訳文(修正後) | This switch turns on the power of the X-ray high voltage generator and the components whose power is supplied from the X-ray high voltage generator. |
|---|
「whose」を使うことにより、「構成品の電源」が「X線高電圧発生装置」から供給されていることが明確に示されます。これにより、文が自然で明確になります。
4. 「whose」におけるよくある間違い④:「whose」を使うべきところに不定詞を使う
| 原文 | 待機画像を変更するデバイスにチェックを入れる。 |
|---|---|
| 訳文(修正前) | Select the devices to change the stand-by image. |
「to change」構文では、「デバイス」がどのように関わるのかが不明確です。この表現は、目的語の関係が曖昧で、実際には「変更するためのデバイス」を指しているように見えますが、「デバイスが変更される」という意味を適切に表現できていません。文の構造が不完全で、意味が混乱しやすくなっています。
| 訳文(修正後) | Select the devices whose stand-by image will be changed. |
|---|
「whose」を使うことにより、「デバイス」の「待機画像」が変更されることが明確になり、文の意味がより明確で自然になります。
5. 「whose」におけるよくある間違い➄:前置詞句を使うべきところに「whose」を使う
| 原文 | 周囲温度が-15 ℃未満または+30 ℃を超える場所 気圧が750 hPa未満または970 hPaを超える場所 |
|---|---|
| 訳文(修正前) | Locations whose ambient temperature is below -15°C or above +30°C Locations whose atmospheric pressure is below 750 hPa or above 970 hPa |
これらの表現では、「whose」によって「場所」が「温度」や「気圧」を所有しているように見えます。しかし、温度や気圧は場所の「状態」であり、「所有」するものではありません。そのため、このような使い方は適切ではありません。
| 訳文(修正後) | Locations with an ambient temperature below -15°C or above +30°C Locations with an atmospheric pressure below 750 hPa or above 970 hPa |
|---|
「with」を使うことで、「温度」や「気圧」がその場所の特徴として示され、より自然な表現になります。「with + 名詞 + 追加説明(前置詞句や関係詞節など)」の形を使うことで、所有ではなく「状態」を適切に表現でき、明確で分かりやすい英語になります。
もう一つの例を見てみましょう。
| 原文 | プルダウンで連携情報が登録済みの重要度を選択する。 |
|---|---|
| 訳文(修正前) | Select the priority whose linkage information has already been registered from the pull-down menu. |
この例では、「whose」が不自然です。「priority」が「linkage information」を所有しているように見えますが、実際には状態を表しています。
| 訳文(修正後) | Select the priority with registered linkage information from the pull-down menu. |
|---|
「with」を使うことで、状態を自然に表現できます。このように、「whose」ではなく「with」を使うことで、意味が明確になり、分かりやすくなります。
6. ほとんどの人が知らないが、知っておくと非常に役立つ文法
2. 「whose」におけるよくある間違い②で、良くない例として「for which」や「from which」が挙げられていますが、実は、このような「前置詞+which」の使い方に関して、ほとんどの人が知らない(おそらく日本の中高大の教育では教えない)非常に役立つ文法があります。最後にそれを紹介したいと思います。
たとえば、以下のような原文があるとします。
| 原文① | このシステムは、機密データが保存される安全な環境を提供します。 |
|---|---|
| 原文② | このアルゴリズムは、検索結果が最適化されるプロセスを定義します。 |
通常、このような文章を「前置詞+which」を使って翻訳すると、ほとんどの人は次のように訳すと思います。
| 原文① | This system provides a secure environment in which sensitive data is to be stored. |
|---|---|
| 原文② | This algorithm defines a process by which search results are optimized. |
確かに、意味も原文と一致しており、文法的にも問題ないため、このままでも問題ありません。また、これが通常、日本の学校で学ぶ関係代名詞や関係副詞の使い方に当てはまると思います。しかし、デメリットとしては、少し冗長である点です。また、テクニカルライティングの観点から見ると、できる限り「is to be stored」や「are optimized」のような余計な受動態は読みにくいため、避けるべきです。そこで、一工夫加えることで、簡潔で読みやすい文章が出来上がります。それが以下の通りです。
| 原文① | This system provides a secure environment in which to store sensitive data. |
|---|---|
| 原文② | This algorithm defines a process by which to optimize search results. |
文法を説明すると、「in which to」や「by which to」は、関係副詞句の目的語として使われる不定詞です。この構造は、場所を示す「in which」や、手段を示す「by which」と「to + 動詞の原形」という不定詞を組み合わせたものです。
日本の英語の参考書ではなかなか見かけない文法なので、最初は違和感があるかもしれませんが、この使い方を覚えて慣れると、とても役に立ちます。
7. まとめ
今回のブログでは、関係代名詞「whose」の正しい使い方とよくある誤用に焦点を当てましたが、実際には「whose」に限らず、関係代名詞や関係副詞の使い方に慣れることが日英翻訳において大いに役立ちます。これらの文法を正しく使いこなすことで、文章がより自然でスムーズになり、翻訳の質も向上します。
特にITやFA分野では、専門的な内容を正確に伝えるために関係代名詞や関係副詞が頻繁に使用されます。これらに慣れておくことで、翻訳の効率が向上し、誤解を減らすことができます。
ヒューマンサイエンスでは人手翻訳サービスやポストエディットサービスを提供しております。ソフトウェア、製造業、IT、自動車、流通と幅広い分野の翻訳を手掛ける翻訳会社です。1994年から長きにわたり多くの企業様の翻訳のお手伝いをしてきました。以下のようなお悩みがあれば是非お気軽にご相談ください。
・翻訳に時間がかかりすぎる!
・品質が悪くクレームが多い!
・翻訳コストが高すぎる!
・日本語マニュアルが原因の問題が多い!
・海外の法律や規格がわからない!
5つのポイントとは?